2024年10月上演の『9 to 5』を語る記事で上田一豪さんに触れましたが、私が初めて観劇した上田さん演出の『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』を語りたくなってしまいました。上田さんの演出の妙、登場人物を描く技について、印象深かったことを語っていきます。
コロナ第1波の影響を受け、初演はわずか1週間の上演。1年半の時を経て果たしたリベンジ公演。わりと古典作品なのに現代の世界でヒヤリとする真実が…!?是非最後までお楽しみください。
登場人物の特徴と描き方
シーモア:三浦宏規さん、鈴木拡樹さん
個性が全然違うシーモアに驚いたが、大切な芯の部分は同じだった。貧困の中で辛い少年時代を送り、自信が全くない地味な青年であること。恋人となるオードリーをしっかり愛していること。前半の登場シーンやオードリーの妄想シーンでは、掃除している姿がよく見られた。
孤児だったシーモアが住み込みで働いている花屋「ムシュニク・フラワーショップ」はスキッド・ロウという名前の貧困地区で、そこでの暮らしぶりを描く「Skid Row」という曲がある。
英語の歌詞で「Where depressions’ jes’ Status Quo(いつもただ憂鬱なのさ)」という箇所があるが、上田さんの訳詞は「幸せが消えた街」となっていた。ハッとするほど胸に刺さる言葉が選ばれている。
英語で歌う映像を見たときは情けなさが強調されていたように思えたが、上田さんが演出する三浦宏規さんと鈴木拡樹さんのシーモアは惨めさが際立っていた。
オードリーに思いを伝える「Suddenly Seymour」は、一途に一生懸命に。「僕は君のヒーローだぜ。守ってやるぜ。オリンなんかより余程いいぜヘヘヘ」というノリではなく、そこここに「こんな僕でいいなら」と、誠実さを滲ませていた。
有名人になっても決して驕らず、自信をつけることもなく、オードリーと幸せに暮らせるならそれでいい、という考えを最後まで通していた。根っからの貧乏性というべきか。
シーモアは全体を通してほとんど笑わない。デーモン閣下が声を演じる人食い植物「オードリーII」のおかげで名前が売れ始めたシーンでは、生活に希望が見えて笑いが隠せない感じがする。
一方オードリーが緑に囲まれたお家でシーモアと夫婦になる妄想をするシーンでは、オードリーの頭の中にいるシーモアが穏やかに笑っている。
でもオードリーに危害を加えるものは誰であろうと許さない。生きることだけで精いっぱいだった彼が、唯一まっすぐな気持ちで頑張れる対象が彼女だったのかもしれない。こんな、一本筋の通った人物の描き方がジンと来た。
シーモア最愛の女性、オードリー
オードリーがシーモアと緑に囲まれたお家で一緒に暮らす妄想のシーン。ここには世界初の演出がつけられている。3Dの映像が見えるサングラスだ。
オードリーが住んでいた家にはあったことがないが、普通の収入がある人は当たり前に持つことができる洗濯機、冷蔵庫、テレビにアイロン。フェンスで囲まれた緑の庭があり、シーモアが芝生を整えている。
そんな、ささやかな幸せを夢見る映像が、舞台上の背景に大きく3Dで映し出されるのだ。「さあ皆さん、サングラスを付けて」というオードリーの誘い声とともに。
私は興味本位でサングラスを途中で外してみたが、あらまぁなんと迫力のないこと。なるほど、3Dの効果がないと、オードリーの頭の中で描かれる夢を同じように見られないのだ。
オードリーはシーモアと同じく貧困に苦しみ、夜の仕事をした過去もある。自分を卑下するあまり、サディストのオリンに引っかかっても自分にはそのくらいの男しか似合わないと、泣きながらシーモアに感情をぶつける場面もある。
そんな彼女が、同じ痛みを分かち合える誠実な男性と一緒に、未来を築いていくことを想像する時間。いちばん幸せを感じられたのかもしれない。それがこの3D映像に表れているようで切なすぎた。
しかし。オリンの暴力で肩を脱臼していたオードリーはそのシーンで腕を吊っているが、歌っているうちに思わず腕を動かし、「痛い!」と言う演出はめっちゃ笑えた。
私は例によってYoutubeでアメリカ版やイギリス版を見たのだが、どのバージョンでもやっていなかったので、おそらく上田さんが作った演出と想像している。
妃海風さんは「あ、いたい…」と呟く。井上小百合さんは「いーーったぁぁ!」と叫ぶ。これひとつ取っても、競うように個性が明確に分かれて面白い。
妃海さんは頭からネジが一本抜けているフワフワ感と、それを反映したような独特の走り方に癒される。井上さんは時々ヘンなテンションになるのが現代のアイドル風かつクセツヨで味わい深かった(笑)。
恋人たちの悲劇
物語の結末としては、狂言回しの3人娘以外の全員が人食い植物「オードリーII」に食べられてしまう。最後の場面でオードリーが犠牲になり、シーモアはオードリーIIを破壊しようと鉈をもって自ら口の中に入った挙句、復讐を遂げることなく消化されてしまう。
オードリーIIが満足げにゲップし、その場は数秒間の静寂に包まれる。
私は予習していたので事の顛末は知っていたのだが、見比べて「だいたいの流れや台詞は一緒なのに演出でこんなにも違うものか」と、ものすごく驚いた。
BW版でのオードリーは最期のシーンもどこか可笑しいというか、あまりリアルに「亡くなってしまった」感じがしなかった。
しかし上田さんの演出では、オードリーはオードリーIIに咬まれて深い傷を負い、シーモアの腕の中でガクリ。これはシーモア…悲しんでも悲しみ尽くせない。
上田さんのインタビュー記事によると、ご自身で脚本を作る時は人の生死について考えを深めることが多いとのこと。そして俳優さんが嘘の世界の作りものを演じるより、本当に自分のことのように自然と心が動く流れを作ろうとしているとのこと。
説得力が強い。だからこういった「ホラー・コメディ」の悲劇的な結末も茶化さないのだ。一生懸命に愛した恋人と引き裂かれた瞬間なのだから、可笑しくなんてできない。なるほどこれが上田さんの最大の持ち味かも知れない。
不運なサディストの歯医者、オリン
子供のころからサディスト男の歯医者。オードリーの恋人。そしてオードリーIIの最初の犠牲者になるのが、このオリン。オリンがオードリーIIに食べられてから、彼は謎の失踪をしたことになっており、オードリーをシーモアが奪い取ることになる。
いやはや、YouTubeで予習したどのオリンよりもヤバイ奴だった。上田さんが演出し、石井一孝さんが演じたオリンは完全にイッちゃってる奴。世界でいちばん彼氏にしたくない男だった。
シーモアが来院する直前まで別の患者の抜歯をしていたので歯医者としては真面目で優秀かも知れないけれど、錆びついたドリルを敢えて使って患者の痛みを増す。
麻酔は患者の痛みを和らげる目的ではなく、笑気ガスを含んで自分でラリッてから治療するために使う。そのラリッてる様子がまあリアルこの上ない。
オリンの最期は第1幕の最後に訪れる。
この場面も、YouTubeで見たブロードウェイ版はやっぱりどこか可笑しかった。しかし石井オリンの演技は背筋がゾクッと寒くなるほど恐ろしかった。
笑気ガスを最大限に吸うために開発した宇宙服みたいな「スペシャル・ガスマスク」が外れなくなってしまい、窒息するオリン。ガスで笑いが止まらないのに息が苦しい。手足が震えてくる。バタッと派手に倒れる。
しかしシーモアがおそるおそる近づくと、カッと眼を見開いてシーモアの足をガシッと掴み、また苦しげに歌い出す。ここでシーモアが悲鳴を上げるが、私も客席で「ヒッ」と悲鳴を上げそうになったのを我慢した。
息絶えるときは目を開いたまま膝をついて動かなくなったかと思うと、シーモアの方にドサッと倒れる。
ガスマスクが取れなくなってしまったために事故で落命するオリン。しかしこれが、シーモアにとってはベストタイミング。なぜなら、彼はオリンがオードリーに暴力を振るったところを目の前で見てしまい、成敗するついでにオードリーIIのエサにしようとしていたからだ。
なんとも都合がよい不運。しかし、可笑しさよりもホラーと人間ドラマの部分が強調されたオリンの結末。衝撃的すぎて頭から離れない場面になっていた。
主人公のソロ曲をぶち壊す電話をわざわざ作る
さて、第1幕の最後で出番が終わるオリンだが、オリンを演じる俳優さんはまだ仕事が終わらない。
第2幕、有名になったシーモアに「一緒に仕事をしてお金を儲けよう」と誘いをかけてくる人々を合計4人、次々と早替えをしながら演じるのだ。この4役は絶対にオリン役者さんが演じる伝統になっているのだそう。
この中で特に個性が強い役が2つあった。
まず、順番では3人目として出てくるスキップスニップ。杖をついた白髪の老人だが、シーモアに仕事の依頼をしてくる。このとき、シーモアはオードリーを幸せにできないかもしれないと葛藤しながら歌っているのだが、その背後で電話をかけるスキップスニップがいる。
海外版ではすべて、歌を邪魔しないように一人で小芝居をしているだけなのだが、石井スキップスニップは電話でベラベラとしゃべっていた。しかも「パパだよ」と、家族に電話かけるんか~い!と失笑するほど、内容がアホすぎる。
シーモアが心の葛藤を歌う合間を縫って、音の切れ目にスキップスニップのアホな話し声が入り込む。
主人公のソロ曲の合間にマイクを入れてこんな芝居を打つのは、上田さんのOKがなければやるはずない。
儲け目当てでシーモアに依頼される仕事は、シーモアが将来も懸命に取り組むようなものではなく、これだけの価値しかない。そんな非情な現実がシレッと感じられるアホさ加減がいい。
オードリーIIとコロナを世界中に広める死神
絶対に書いておかなければいけないのは4人目の男、パトリック・マーティン。
この男は作品の中で一番恐ろしい。オードリーIIの葉っぱを剪定して小さな植木鉢に分け、世界中に出荷しようとするマーケターなのだ。つまり、人食い植物が世界中に広まる。
石井さんのSNSかどこかに記載されていたが、マーティンの演技には上田さん指導のポイントがあるらしい。マーティンは分かりやすい悪党ではなく、穏やかで真面目でいい人そうな雰囲気であると。しかしその腹の中には黒い野望を持っていると。
これに従い、確かにマーティンが最初に出てきたときは物静かで普通の有能なマーケターに見えた。しかし彼の最後の台詞で物語を閉めるとき、オードリーIIの「出荷作業を始めよう」と言う。
このとき彼の眼が静かに、ちゃんと見ていないと分からないほど静かに、悪魔に変貌する。「死の商人」と石井さんは表現されていた。
鳥肌が立った。この作品の初演はコロナが始まった直後で、たった1週間しか上演できなかった。私が観るはずだった公演も流れてしまった。そこから1年半。まだまだマスクと体温計測が必須、既成退場もしていた再演当時。
私にはパトリック・マーティンがコロナを世界中に運んだ「死の商人」に見えた。
コロナも自然のものだか陰謀論だか色々出ているし真相は知りたくもない。しかしこの最後のシメのおかげで、あのパニックと憂鬱でいっぱいの数年間において、あまりにも時節に合いすぎる作品だと思えた。
人の感情の機微と時代を捉える演出
上田一豪さんがコロナ禍の真っただ中において、ウイルスをオードリーIIに置き換えて描いたような作品『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』。改めて振り返ってもすごい作品、素晴らしい演出だった。
登場人物を表現することにおいては、感情の機微もその人が背負ってきた人生も、ほんのちょっとした力加減で鮮やかに浮かび上がらせる。物語を伝えることにおいては、上演される時代を物語の中に映し出す。
残念ながら最近は彼の作品を拝見できていないが、次の『Play A Life』や『この世界の片隅に』の再演があったら是非観なければ。皆様のオススメも是非教えてください。

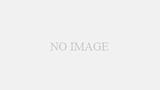
コメント