2024年1月に生まれたてホヤホヤの日本産ミュージカル『イザボー』は、あらゆる意味で「新しい」「世界に撃って出る」を強く意識した作品。今までの型にはまりたくない、つまらないと感じるものを解消したい、そんな気概を随所に感じられた。
『イザボー』を語るシリーズ第2弾は演出について。自在に場面を転換させるセット、客席参加の極意、そしてミュージカルを観慣れた人を驚かせる粋なカーテンコールについて取り上げます。
ぜひ最後までお付き合いの上、客席の興奮を一緒に感じてください!
『イザボー』舞台演出の魅力① 演者さんと場面に魂を吹き込むグルグルセット
そんな「新しい」演出で中心となったのは、舞台の盆を占領するセット。「グルグルセット」と呼ばれているらしい。何度も乗っていたら気持ち悪くなるんじゃないの?なんて思えるこれが信じられないほど素晴らしい機能を発揮した。
基本的な見た目はゴツゴツの石造りで、いかにも中世の古城や砦といった感じ。ヒンヤリとしてカビ臭くて、煮炊きをした煤の汚れなんかがあるかな?と想像を掻き立てられるような古めかしさ。
その石壁が冒頭からおもむろに回りだし、登場人物やダンサーたちが窓という窓から顔を出せば、もう一気に心が600年前へタイムスリップだ。
プリンシパルがグルグルセットから様々な角度で1人ずつ登場する時、もしくは1列に並んだ時、イザボーは真っ赤なドレスでほかは全員黒と銀。
うわあどうしよう。興福寺国宝館の天界八部衆にそっくり。あるいは新薬師寺の十二神将でもいいぞ。
どちらにせよ歴女を興奮させるに十分だった。生身の人間なのに、そこが生きる国宝館と化したような錯覚さえあった。
さらに石壁はザックリと2つに割れる。階段が客席側に向く角度が違うだけで、舞台全体が街の建物や城の中庭、ときに抽象的な空間にも変化する。しかもあらゆる場面で、人力で回転させる。
これさえあれば場面ごとのセット転換が最低限ですむ優れもの。見事すぎる。
『イザボー』舞台演出の魅力②「参加型」で観客を物語の世界に引きずり込む
シャルル・セッツ!!戴冠式見物の群衆になるべし
客席参加型ミュージカル。これは決して珍しくない。しかしこの作品での客席参加は、定番の手拍子だの一緒に踊るだのの一歩上を行く。観客が物語の中に巻き込まれてしまうのだ。
まずは冒頭から大興奮。開演前アナウンスから、すでに観客はシャルル7世の戴冠式の見物人にさせられている。ダンサー2人が客席に向かって「ここに集まりしフランス臣民たちよ」(※決して正確な台詞ではありません)と声をかける。
あら、わたしたち?と思う暇もなくボケとツッコミだらけの諸注意を行う。
携帯電話とかアラーム付きの腕時計とか、ヴァロワ朝のフランスに存在しないものは電源を切れ。さもなくば断頭台送りだ。って断頭台もこの時代にないでしょ!みたいな(笑)。完全にコントになっていて面白すぎる。
そしてダンサーさんたちが客席通路に現れ、みんなで新しき王に「シャルル・セッツ(シャルル7世)!」と声高らかに呼びかけよと命じる。その声が大きく盛り上がるのを見計らい、グルグルセットが回転しだす。佇むシャルル7世。プロローグの曲が始まる。
これをやられた観客はたまらない。平日の夜、仕事の疲れも現実も、この時点で吹っ飛ぶ。
ジャン・サン・プール裁判に傍聴人として出頭すべし
もう1つは2幕の中盤に来る。ブルゴーニュ公ジャン(中河内雅貴さん)がオルレアン公ルイ(上川一哉さん)をあの世に送った罪に問われ、裁判にかけられる場面。
ジャンは「恐れ知らず=サン・プール」と異名がついており、豪胆公と呼ばれた父の血を色濃く受け継いでいる。彼がいかに大胆不敵かが一番よく分かるのが、この裁判シーン。
被告人ジャンの目の前には、なんとスタンドマイク。ジャンはそのスタンドマイクを握り、ロックシンガーのごとくアップテンポな答弁をおっぱじめる。
客席を回りながら堂々と自分の正当性を述べれば、あら不思議。あっという間に観客は裁判の傍聴に来た群衆と化している。
同じく傍聴人のダンサーの皆さんも、裁判長も、私達観客も、気づけばみんなで手拍子をしている。ジャンも「もっともっと」と合図をしてくる。
空気はライブ・イン・アリーナ。内容はしっかりお芝居。気分はパリ市民。最高だ。
ここまで手の込んだ「客席参加型」は前代未聞であると思う。客席参加は私が覚えている限り、一緒に手拍子するとか、カーテンコールで一緒に踊るとか、お芝居の外枠で行うものだった。しかしこの作品は、物語の中にエキストラとして観客を引きずり込む。
しかもごく自然に、知らぬ間に。楽しすぎる。
『イザボー』舞台演出の魅力③ パーティーとカーテンコールに思わぬ人物が
バンドがパーティーに参加してる!
この作品では舞台上に思わぬ人物を見かけた。キャストでない方々が客席の喝采をかっさらう場面がある。
まずは1幕中盤、パーティーの場面がある。登場人物やダンサーさんたちが楽しく踊ったりお酒を飲んだりしている中、楽器を持っている人が何人か出てきた。
おお、そうだよね。DJとか録音を流せる音響機材がない時代、パーティーではオーケストラの生演奏。だから演奏家の役かなと思っていたら…
あれ?衣裳じゃないぞ。黒服でキャストさんの空気感に合わせてはいるが、髪型もお化粧も服装も、明らかに14世紀のフランス風ではない。
なんとバンドメンバーの皆様ではないか。舞台裏から出てきて、リアルに現場の演奏家としてパーティー会場にいるのだ。
ブルゴーニュ公フィリップ役の石井一孝さんは普段から楽器大好きなので、さっそく演奏家の一人と肩を組んでいる。もちろんフィリップとしての演技の一環だ。
これはいい。いないよりもずっとパーティーの空気感が盛り上がる。決してライトを浴びることがない舞台裏の方々をこんなふうに生かすことができるとは。
カーテンコールがすごい人数!
最後にどうしても書いておきたいのは、カーテンコールに出てくる皆様。ほかの作品だったらプリンシパルキャストは1人1人、もしくは登場人物の中で同格の2~3人が一緒に出てきて挨拶するのが定番である。
しかしこの作品はキャストの紹介を早々終えてしまった。お?と疑問に思う間もないスピード感で、スイング(もしもの時に代役をいつでもできる若手)、音響、グルグルセットを回していた大道具さん、バンド、照明、そして最後にイザボー。
このカーテンコール、ダンサーの皆様は山盛りになったバラの花びらにダイブする。キャストもスタッフの方々も、お互い頭から花びらをかけ合う。客席にもかける。みんなを祝福している。
カーテンコールで観客の拍手を浴びるのは舞台の上に立っている人だけではいけない。裏で支えている人たちがこんなにいるんだぞ。この人たちが一瞬でも輝かなくてどうする。拍手を浴びなくてどうする。
そんな声が聞こえてきそうだった。なんという心意気だ。世界中探してもこんな感動的なカーテンコールはないのではないか。
世界で唯一の個性的な演出
1台で七変化するグルグルセット。
物語に引きずり込まれる客席。
普段は舞台上でなかなか姿を見せることのできない縁の下の力持ち。
この作品が世界に出るときの付加価値として、どれも欠かせない。新しいが決して風変りではなく、誰もが受け入れることのできる温かさがある。今まで何故やってこなかったのだろうと思えるほど。是非とも世界中に評価されたい。
だから、ね。やっぱり早く世界に出ましょう(笑)。

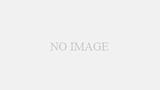
コメント