私が好きなミュージカルNo.2に君臨する名作『ウィキッド』。
この記事では『ウィキッド』原作小説の上巻をもとに、ミュージカルの予習にぴったりの背景情報をご紹介。エルファバの幼少期と家族、シズ大学での学生時代、オズの陛下に反旗を翻すまでを追う。
是非最後までお楽しみください!
ミュージカルで描かれているエルファバの人物像についてはこちらの記事をどうぞ。
おどろおどろしく描かれたエルファバの誕生
2024年11月(日本では2025年春)から公開される映画版は2部作。ということは、もう少し原作に沿った内容になっているのではないかと推測し、思い切って小説に手を出した。
面白すぎて見事にハマった。なんで今まで手を出さなかったんだ…猛反省。
原作小説ではエルファバの家族構成がミュージカル版とだいぶ違うので、まずそこから行ってみよう。
まず、父親はユニオン教という古き良き宗教の牧師。快楽信仰に走る人々に布教活動をしても手ごたえが掴めず苦しんでいる。ミュージカル版ではマンチキンの総督となっているが、小説ではマンチキン総督は、エルファバの母方の曽祖父。エルファバはマンチキン総督の4代目だ。
妹のネッサローズは、ミュージカルでは足が悪く車椅子生活とされている。原作では両腕もない。父親の信心深さを引き継いでいるので、話がいつも神様の道徳につながる。姉が姿をくらました後は特に、自分を見捨てた姉を恨んでますます信仰に傾倒していった。ついでにシェルという弟もいる。
エルファバが生まれたまさにその夜、父親は快楽信仰の象徴「時を刻むドラゴン時計」のいかがわしい見世物に夢中になっている人々のところへ布教に出かけた。結果、暴力まで振るわれ散々な目に遭った。
エルファバの父親と騒動を起こした酔っ払いたちが走り回る中、自宅が危険だと判断したエルファバの母と手伝いの女性たちは家を出る。なんと彼女らは、林の奥に置き去りにされたドラゴン時計の中に忍び込んで出産する。
ドラゴン時計の中で生まれた赤ん坊
ドラゴン時計。ミュージカルを観たことのある方は一瞬でお分かりだろう。
そう、舞台の上方ど真ん中を陣取り、技術さんが観客から見える位置で操作する、あれだ。
オーバーチュアとともに赤い眼をきらめかせ、口から煙を吐いて暴れまくる、あれだ。
舞台脇にいくつも歯車があったのも覚えておいでだろう。
あのドラゴンがエルファバをずっと見ていたのだ。
エルファバは産声を上げなかった。何かの間違いかと思ったが、どう見ても肌は緑色。すでにサメのような鋭い歯が生えており、女性の一人が口元に近づけた指を噛み切ってしまった。そしてドラゴン時計の歯車をじっと見つめた。
父親にとっては仕事で失望して家に帰ったところに、緑色の肌の娘が生まれていたわけだ。呪われているのかと、悪魔祓いもしてみたが緑の肌は治らなかった。牧師として自分の仕事が足りないのかと考え、妻子を置いて布教と苦行の旅へ出てしまう始末。
母も自分の子を受け入れられず、自分の乳母を呼んで世話係を任せ、睡眠薬ばかり呑んで現実逃避する日々。そこへ貧困地域から旅をしてきたガラス吹きの男と浮気してしまう。
母の愛人は父が帰ってきても、怪しい関係を隠しながら家にずっと居候した。その男と話している間に、父は貧困地域での布教をするため移住を決意。それ以来、エルファバはシズ大学に入るまで貧困地域で育った。
これがエルファバの誕生と幼少期。ミュージカルではサラリと曲の中で描かれているだけだが、実はこんな恐ろし気なエピソードだった。父がドラゴン時計のせいで踏んだり蹴ったりの夜、ドラゴン時計に見守られながら生まれてきたのだ。
生まれてすぐ血の味を覚えたり、初めて発した単語が「きょうふ」だったりと、あらゆる意味でタダ者ではない。
誰にも祝福されず、愛されずに生まれ、前途多難な将来が約束された緑色の子供だった。
グリンダ、ボック、ディラモンド先生との出会い
さて、ここから一気に物語はエルファバが学生時代を過ごしたシズ大学へと移る。最初はグリンダの視点で入学時からの様子が描かれ、そこからボックの視点へ、エルファバの視点へと変わっていく。
グリンダは、民族の由緒正しき発音でいうと本当はガリンダという名前のようだ。改名の理由は、魔法使いの弾圧のせいで退職に追いこまれた大学の恩師、ヤギのディラモンド先生が「ガリンダ(Gulinda)」と発音できなかったことから、グリンダ(Glinda)と名乗り始めたこと。
実はこれ、ミュージカルでも英語版だとそうと分かるが、日本語では省略されている。
英語のつづりで見ると分かるように、「ガ」はGの後に母音が続くが「グリ」は子音が2連続する。この2つは英語での発音は異なるが、日本語では「あ行」の「ガ」か「う行」の「グ」の違いだけ。ほとんど変わらない。
この「ガ」VS「グリ」を、英語の綴りを読むことができない舞台で、しかも日本語で議論しても観客にはなんのこっちゃか分からない。こういった理由で「ガリンダ」が「グリンダ」に変わるエピソードは削除されたのだろう。
そのディラモンド先生とグリンダとの出会いは、入学する時の列車の中で相席になったこと。ご存じ、ディラモンド先生はヤギなのだが人間の頭脳を持っている。ほかにも様々な動物が、人間の頭脳を持つタイプとそうでないタイプに分かれている。
しかしオズの魔法使いがオズの国を支配するようになって以降、動物は迫害されている。電車の切符が使えないようになり、移動や職業選択が制限されている。その弊害と怒りを、ディラモンド先生は出会ったばかりの入学生にくどくどと説教するのだ。
ディラモンド先生は、ミュージカルでは歴史の先生。しかし原作小説では生命科学の研究者で、動物の弾圧がいかに間違っているか、倫理に反しているかを生命科学的に証明しようとしていた。
つまり、生物学的に…と言いたいところだが違う。オズの国の世界観は我々が生きている現実の世界とだいぶ違い、妖精やら魔女やら、半分神話のような歴史と宗教観に強く影響されている。
エルファバは彼の考えに共鳴し、ディラモンド先生を指導教官に生命科学を専攻する。
グリンダは先生の第一印象が悪かったこと、自分の希望に反してルームメイトになってしまったエルファバが決して好きではなかったことから、生命科学は選ばなかった。
代わりに専攻したのが魔術。たいして才能はないと早くから分かっていたが、つまり魔術は特殊能力ではなく、小説ではオズの国に普通にある学問として捉えられていたことが分かる。
そこにボックが登場する。ミュージカルではグリンダに恋をする小柄なマンチキン族とだけ描かれていたが、エルファバが物心つくかつかないかの頃に一緒に遊んだ仲。グリンダに出会った当初は首ったけだったが、徐々に薄れていったと描かれている。
ボックとエルファバはディラモンド先生の研究を手伝うため、夏休みを図書館の調べものやカフェでの勉強会で共に過ごした。一緒に遊ぶ相手や恋愛対象には決してならなかったが、同じ志を持つ仲間として描かれている。
ディラモンド先生がまさかの!急展開とエルファバの目覚め
しかし事件が起こる。ミュージカルしか知らなかった人はここで大ショックを受けることになる。
ディラモンド先生は、ミュージカルでは弾圧のために退職させられた。小説では信じがたいことに、命を奪われてしまう。無残なやり方で。
犯人はほかでもない、マダム・モリブル。彼女はオズの魔法使いを崇拝し、魔法使いのために動くスパイである。
この事件の後しばらくして、マダム・モリブルは正体を現す。エルファバ、グリンダ、エルファバの妹ネッサローズを呼び出して手先になれと言うのだ。彼女らの素質を見定めてのことで、おまけに口外できないよう呪文までかけて極秘任務を明かした。
グリンダとネッサは呪文にかかったが、エルファバはかからなかった。彼女はすぐさま行動を起こした。ネッサをほかの学友たちに託し、グリンダを引っ張ってシズ大学を抜け出し、オズの魔法使いのもとへ直談判しに行ったのだ。
ミュージカルでは魔法の才能をマダム・モリブルに認められ、念願叶ってオズの魔法使いに会いに行くエルファバだったが、小説は随分と違うので一番驚くかもしれない。
謁見してみたオズの魔法使いは、エルファバの主張に耳を貸さなかった。玉座からエルファバとグリンダを見下ろし、終始バカにしていた。
エルファバはついにブチ切れる。グリンダだけを帰りの馬車に乗せ、お別れを言い、二度とシズ大学には戻らなかった。
ミュージカルの印象がガラッと変わる!哲学満載の原作小説
ここまでがエルファバの学生時代として描かれている。ほかにもここには出せなかった学友たちや乳母たちが複数いたり、若者らしいエピソードや伝統校あるあるの厳しい校則や恩師なども。
生命科学は森羅万象の分析であり、魔術はそれらを使った芸術であるという哲学も語られる。オズの世界の神話や歴史も、要は多神教なので非常に独特。図書館で見つけ出した歴史書や絵画から示唆されていることを読み取ろうと、エルファバやボックが奮闘するシーンもある。
ミュージカルでエルファバがオズの魔法使いに反旗を翻すのは第1幕ラスト。動物の迫害を目の当たりにしたうえ、オズの魔法使いに本当は魔力などなく、魔力を持つエルファバを支配の手先にしようとしていると分かったからだ。
しかし原作小説では、この時点でエルファバは魔女として描かれていない。彼女に魔力という特殊能力があるとは、少なくとも上巻では一言も書かれていない。だから、猿に羽根を生やす呪文もかけなければ箒に乗って飛び去ることもしていない。
その代わり印象的なのは、エルファバの複雑で重苦しい家庭環境と、すんごい論理的な発言の数々。
エルファバはめちゃくちゃ理屈っぽい。「可愛げのある」とされる女の子をにありそうな、優しい言葉や優雅な身のこなしなどは全く描かれない。そんなものは緑の肌のあたしにはカンケーないと言わんばかりに。代わりに、相手を論理で黙らせる。
そして物事を、社会の常識を、他人の発言を、裏の裏まで読み解こうといつも努力している。表面に惑わされることは決してない。
いい。とてもいい。こういう子と友達になりたい。表面的な世間話なんかより余程学びの多い人間関係を築けそうだ。
【次回予告】小説を読み解くシリーズ、まだまだ続きます。第2回はシズ大学から姿を消した後のエピソードをご紹介。こちらからどうぞ!

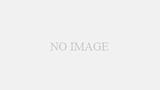
コメント