ついに観てきました『next to normal』!!!
念願の初観劇でした。観て良かった!ものすごい作品でした!衝撃作にして問題作。まだご覧になっていない方々、どうか劇場でこの物語に没入してください。
この記事では、キャストさんそれぞれの感想および登場人物と物語についての考察をまとめました。是非最後までお楽しみください。
ダイアナ/望海風斗
すごかった。本当にすごかった。華やかなトップスターの印象をぶち壊して、現代を生きる等身大の女性に体当たりした演技。かつてないほど感情移入したかもしれない。
かっこよくない望海さん。豪華さや美しさで魅了しない望海さん。アメリカの郊外で暮らすごくごく平凡な母親の望海さん。
2024年の現代、リアルにその辺にいそうな普通の母親だった。長い人類史の中、まるで神格化されたような理想的な母ではなく、現実の生活と戦う一人の女性。
この作品は双極性障害への理解を深めるという点では社会的に役立つ教材だ。しかし、1人の女性の物語として見るなら、女性が母になるといかに母という役割に縛り付けられるかがよく分かる。
大切な人との間にできた大切な赤ちゃんを守れなかった。先入観のせいで異常を見逃した。大人のせいで助からなかった我が子。どうすれば良かったのかをずっと考えていたら、どういう結果だったら良かったかに頭の中がすり替えられてしまった。
そうして、助かった我が子が平凡に育っていく幻影を見るようになった。
でも妻としての役割をちゃんとしなきゃという意識があったり、2人目を生んだら愛情を向ける対象ができて症状が回復するかもという希望を持った。なのに、2人目もまた失うのではないかという恐怖に駆られた。
そして結局は疾患から脱することができなかった。夫と娘のために明るい家庭を保たなければという義務感と、息子を失ったという消せない悲しみが、どんどん二極化してしまった結果がこれだ。
女性は一度母親になってしまうと、母親という自分のアイデンティティから抜け出せない。育てることをあきらめて施設に預けたり里子に出したりという選択肢が思いつかない限り、生んでしまったものは責任もって世話をしなきゃと思う。
たとえ育てたくなくても。育てたいと自分に言い聞かせざるを得ない状況になっている。対する娘も生まれた時から世話をしてくれている母が愛しいし、愛してほしいと思う。それが普通だから。
お互いがお互いを役割で縛っていた。だからこそ、日々の生活をこなすことだけで精いっぱい。心から語り合うことなんてできなかった。初めて向き合えたのが、「Maybe/ Next to Normal」を歌ったときだ。
つまり、ダイアナが向き合う「べき」家族から解放されるときだった。息子の記憶を一時的に失い、それが戻ったことにより、見えていなかった目の前の大切な娘がやっと見えた。同時に、役割に縛られていたことにも気づいた。
一度、全部あきらめて解放されよう。そうすれば今までとは違う自分になれるかも。そうして思いきって家を出る決意ができた時、相互依存の関係にあった夫も、義務で育てていた娘も、大切で愛しい存在だと分かった。
心からそう思えたから、ラストシーンのダイアナは爽やかな笑顔をしていたのではないだろうか。
こんな一連の考察ができるのは、ひとえに望海さんによる演技のおかげ。ブラボーです。
ダン/渡辺大輔
渡辺さんのパパ役は初めてだったが、娘の頭をなでる姿にやたらホッコリしたのは私だけだろうか。夫としては、上から目線ではなく隣で肩を並べてくれる温かい男性に見えた。ダイアナが電気ショック療法の同意書にサインするときの説得の仕方なんて、本当に理想的だった。
精神を壊した妻を支える側に徹していた夫。娘を普通に育てたくて、ときどき使い物にならなくなる妻の代わりにしっかり頼りになる存在であろうと努力してきた。
ヘンリーを夕食に招いたときのバースデーケーキ事件で大喧嘩になったのは、支えても支えても自分は報われず息子の幻影ばかりにすがる妻に対して、張りつめていた糸が切れてしまったのだろう。
分かる。すごく分かる。身内だからこそ介護は難しい。精神疾患にしても他の障がいにしても認知症にしても、自分の努力の量と相手からの感謝や回復度は、必ずしも比例しない。赤の他人で介護のプロだったら、逆に割り切れる。でも身内だとそうはいかない。
ダンのことを自分中心の人物として批判する人もいるようだが、少しでも身内の介護を経験したことのある人ならダンの気持ちは他人事ではないはずだ。少なくとも私には彼を責めることなんてできない。ダイアナを一番近くで守り、病院に送り、宥め、手をつないで歩いてきたのは彼なのだ。
だから家を出るダイアナを見送ったときのダンはいたたまれなかった。椅子の上でうなだれ、一回りも小さくなってしまったような肩。そこにゲイブが現れる。
ママは先に進める。でもパパの時間はここで止まるの?止まっちゃだめだよ。僕はパパのこと分かってるんだよと。
父と息子、涙のデュエットに私もブワーッと涙が出て止まらなかった。
息子の幻影は妻の疾患の原因だからと遠ざけてきた。だから、ちゃんとお別れできていなかった。健康に育っていてくれたらという後悔は決して消えていなかった。幽霊でも何でもいいから息子に会いたかった。
妻が自分を置いて出て行ったとき、そんな思いが一気に押し寄せたのかも知れない。そしてやっと、妻だけが見てきた息子と会えた。
あんな渡辺さんの泣き顔、泣かずに見られるわけない。
ゲイブ/甲斐翔真
甲斐さん演じるゲイブ、こちらも等身大のティーン。『イザボー』のシャルル7世で見せた貴公子っぷりを封印し、どこにでもいそうな青年だったのが親近感マシマシだった。背が高いのでアメリカン・スタイルな白いスニーカーがめちゃくちゃ似合う(笑)。
ゲイブの一挙手一投足はすべて、生きている人の頭の中で描かれている。「I’m Alive」を歌って猛烈に自己アピールするときさえ、もうこの世にいないゲイブの意思ではない。ダイアナの頭でゲイブが「忘れないで」と主張しているのだ。
ダイアナにとってはちょっとだけ悪ガキだけど親孝行な息子。ダメなところもあるけれど可愛い息子。当たり前に育ってくれた平凡な息子。ナタリーにとっては、顔も知らないのに母から自分を奪おうとするスーパーマン。ダンにとっては、一人残された自分を救ってくれる最後の存在。
特にダイアナにとっては、本当にやりたいことをゲイブが代弁してくれる。ダイアナはゲイブがアドバイスしてくれたから薬を捨てた。ゲイブが一緒に向こうの世界へ行きたいと言ったから手首を切った。
ダイアナとはぎゅーっと抱き合って踊るけれど、ダンには後ろから抱きつくだけしかできない。最後に名前を呼んでくれた時だけ、目の前で顔を向き合わせた。すべて、生きている人がゲイブにやってほしいことだった。
人間を超越した存在としてのゲイブ。自分の意思を持たないのに強烈なゲイブ。生きてはいない、でも幽霊なんかじゃない、一体何者なのだと震えが来るくらい甲斐さんの存在感は迫力満点だった。
ナタリー/小向なる
小向さんは初めて拝見したが、こちらも本物の高校生を見ているような自然体すぎる演技が本当に良かった。まあついこの間まで高校生だったよね、ナタリーの気持ち分かるよね、なんて思ったくらい自然にハマっていた。
繊細で多感なティーンにとって母親の愛情は欠かせない。まだまだ抱き締めてほしいし、進路やら学校の人間関係やら話したいことだって山ほどある。女性としても自分の鑑でいてほしい。
そんな母親は生まれた時から異常で、ナタリーはいわゆる普通の母を知らない。自分に遺伝しているかも知れないという不安もだんだんと強くなる。早くここから出して、不安から解放して、と思うからピアノを頑張っている。
なのにリサイタルに両親は来てくれない。母はもういない兄ばかり愛して自分は透明人間みたいだし、父は母のケアがいつも優先だし、あげく母は頭に電流を流されるし…。
グレたくもなるわな。ヘンリーが言った通り、自分で自分をぶっ壊していた。
ナタリーとヘンリーは『Dear Evan Hansen』に出てくる少年少女とよく似ている。複数の抗うつ剤を服用し、ムシャクシャするからドラッグに依存しナイトクラブに入り浸る。
これはなにもアメリカだけの社会問題ではない。日本を含む様々な国で、精神疾患や発達障害を持つ子供は早い時期から薬漬けになる。ドラッグは少し酷い例かも知れないが、一歩間違えればこうなる。
そんな辛い時期があったから、ナタリーとダイアナが初めて正面きって歌った主題歌は息を呑むほどの緊迫感で、最後は涙が出た。ずっとナタリーの胸の中で滓のように、ゴミのように溜まっていたわだかまりが、スッと抜けたのが見えるようだった。
普通がそもそも分からない。でも、良くなると信じている。普通の隣りくらいがしっくり来る。それでいい。
このときに母娘が分かち合った「良くなる」状況は曖昧だけれど、決して疾患が回復することではなくていいと思う。笑顔でできる会話が増えたり、お互い素直になれたりすることで十分。
「普通の隣り、next to normal」という言葉がダイアナではなくナタリーの口から出たというのがミソだ。ティーンの頭の柔らかさが発揮されたというべきか。ダイアナという当事者ではなく、その娘の視点だから出てきたというべきか。
ダイアナは娘のその言葉を聞いて心がどれだけ軽くなったことだろう。ナタリー、よくやった。
ヘンリー/吉高志音
吉高さんも初めて拝見したが、なんて柔らかい物腰の、優しそうな好青年。
予習しかしていなかった段階と観劇後にいちばん大きく印象が変化したのがヘンリーだった。それは吉高さんの演技が説得力抜群だったことに尽きると思う。
私は英語版で予習したとき、注意欠陥多動性障害という病名が聞き取れていなかった。そうか。この子もADHDだったのね。そういうことなら、すべてが1本に繋がる。
ヘンリーは精神的な不安定さにも服薬にも慣れている。自分こそが当事者だから。ちょっと危ないドラッグにもすでに手を出している。だからナタリーに惹かれたし、悩む気持ちも分かるし、平日夜にクラブからクラブへ連れ回されても怒らないのだ。
ナタリーは家庭環境の影響で抑うつ状態になったり混乱したりと、だいぶカッコ悪いところをヘンリーに見せる。いちばん人に見られたくない自分の姿や家庭の事情だ。いわゆる普通の男の子なら、好きな女の子のそんな面倒臭い一面を見れば逃げていくだろう。
でもヘンリーはナタリーが苦しむところを見れば見るほど愛しくなってしまった。君は自分をクレイジーというけれど、それを言うなら僕だって。2人ともお互いにパーフェクトだよ。ナタリーにそんなことを心から言えるのは、彼だけだ。
ヘンリーがナタリーをガシッと抱き締めるところで涙ぐんでしまった。白馬の王子様なんかじゃなくていい。お互い別々の事情を抱えているから前途は多難だろうけれど、手をつないでマイペースで歩ける人がいいの。偉いよ。優しいいい子だよ。
ドクター・ファイン&ドクター・マッデン/中河内雅貴
中河内雅貴さんはダイアナの主治医2人をお一人で演じた。『イザボー』のジャンの面影が頭に残る私としては、没個性な感じのするこの役を中河内さんがやったら魅力半減?と思いきや…やはりロックシンガーなみに壊れる瞬間が。
演じ分けっぷりもさることながら、特に静かな存在感が素敵だった。少なくとも今まで拝見した中河内さんの役では、初めて「ダンディ」という言葉が似合うと思えた。
最初に演じていたドクター・ファインは、ダイアナがドクター・マッデンと出会う前にかかっていた精神病理学者。マッシュルーム頭と眼鏡と髭とヘンな声で、だいぶ気持ち悪い風貌だ。
中河内さん曰く、薬オタクの研究者。なるほど。名前のファインは英語だと「いい感じ」「まあ大丈夫」くらいの意味になるので皮肉たっぷり。
一方ドクター・マッデンはマッド・ドクター、つまり「イカれた医者」という意味を彷彿とさせるが、いかにも誠実で真面目な感じ。しかしやはり、電気ショック療法を提案することがマッドなのだろう。特にダイアナとナタリーにとっては。
初登場の場面は確かにイカれた感じに見えたが、ファンキーでセクシーで危険な男に変身するのは一瞬だけ。その前後はいたって普通の医師。つまりあれはダイアナの頭の中で描いたドクター・マッデン。ああいうヤバイことをされているような印象を受けたのだ。
精神科の医師としては、やはり辛い場面もあった。心の治療は、医学界でもっとも最適解が少ない分野なのではないだろうか。最後にダイアナがドクター・マッデンと決別するシーンは、ダイアナよりもマッデンに感情移入した。
医師は失敗も含め淡々とデータを保存し、次の治療への戒めとすることしかできない。ダイアナもまた、医学界に積み上げられる膨大な事例の一つでしかない。
自分はプロとして患者と向き合った。でも感謝されるとは限らない。最善の道と信じたものが大外れの時だってある。感情を挟んだら損をする。でも、患者への思いがなければ仕事なんてできない。
中河内さんの何とも言えない切ない目をしたマッデンを見て初めて、この物語は当事者や家族の話だけではなく、医師の気持ちにも目を向けることができる作品だと気づいた。
台詞や歌としてほとんど描かれていないので、どうしても焦点はマッデン以外の登場人物に向きがちだ。しかし観客としてこの作品を観たお医者さんや研究者さんは、マッデンの考えが手に取るように分かるに違いない。医師は自分の感情を押さえつけて患者と共に戦っている。
正解がないことを受け入れ、前を向くことの大切さを教えてくれる
6人という少ないキャストで濃ゆい物語を紡ぐこの作品。ミュージカルの可能性を広げたと評価されるのも納得だった。
カーテンコールでキャストさんの1人が思わず「普通が一番ね」と語り、「え!この作品やったのに!」と他の方に突っ込まれるというホッコリな時間があった。
そのくらい、キャストさんもこの物語と登場人物に向き合うために七転八倒されたとお見受けした。当事者でなければリアルに体験できない疾患ではあるけれど、どこにでもあること。
ドクター・マッデンの選択、ダンの判断、ナタリーとヘンリーの恋、ダイアナの決断。物語が迎えた結末が最適解であったかどうかは分からない。だって、誰も正解が分からないのだから。
それでもラストシーンで全員がそれぞれの場所で笑顔になれたのは、みんな一歩だけ前に進むことができたからだ。
誰であってもどんな状況下にあっても、幸せになりたいと願うのは当たり前。幸せを諦めずにゆっくりと歩いて行けば、それぞれが思い描く光が見えてくる。
重い物語の後で明るく終われるのは見事としか言いようがない。この作品を生み出した方々に今は心から感謝しているし、この作品がもっと広まっていくことを願ってやまない。

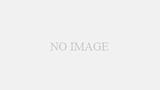
コメント