劇団四季オリジナルミュージカル『ゴースト&レディ』を語りまくるシリーズ第3弾。ナイチンゲールの人生を掘り下げるの巻、後編です。
フローレンス・ナイチンゲール(フロー)といえばクリミア戦争。ミュージカルでもクリミア戦争が中心でした。しかし従軍看護師だった期間はたった2年。実はその後の人生の方が長く、色濃かったのです。
作品中に描かれていた、ちょっとした台詞が今も看護理念になっている!
あんな人との事件が人生に重い影を落とした!
こんな人のエピソードが今も医学用語で使われている!
そんな、見過ごされがちな彼女の本当の凄さを紐解いていきます。是非最後までお楽しみください。
『ゴースト&レディ』クリミア戦争の野戦病院でナイチンゲールが受けたデオン・ド・ボーモンのナイフがその後の人生を左右した
ミュージカルの中でフローは、フローの活躍を阻もうとするジョン・ホールの命を受けた決闘代理人デオン・ド・ボーモンのナイフを受け、生死の境をさまよう。
生きた人間が幽霊にやられるって、虚実織り交ぜるにしても随分と話を盛ったな…ジョン・ホールが黒幕の暗殺未遂事件でもあったのかな?と思ったのだが、劇中では「原因不明の病」とされていた。
グレイが自分の霊力をフローに与えたおかげで一命をとりとめるが、本当に奇跡的な回復だったに違いない。
原因不明の病の正体はなんと、クリミア・コンゴ出血熱という感染症。ダニを介して感染するウイルス性の熱病で、出血を伴う。今でも特効薬やワクチンは開発されておらず、致死率は高いらしい。
なるほど~病院は不潔だったからね~!!フローはクリミア戦争の野戦病院で、衛生状態の悪さを指摘し改善したが、自らもこんな感染症にかかっていたのだ。
病院の衛生管理が行き届かなくては患者だけでなく医療従事者の命まで脅かす。この現実を痛感したことだろう。
帰国後も後遺症に悩まされながら、クリミアでの学びを活かしてイギリスの陸軍や教育、病院機構の改革を推し進める。
しかし40歳で慢性疲労症候群を発症。全身倦怠感や抑うつ状態、思考力の低下、微熱や体の痛みが長期間続く病で、感染症が引き金になることも少なくないらしい。
フローは出血熱の後遺症を抱えながら仕事を続け、ストレスの多い生活を送っていたのだから尚更だった。81歳でとうとう失明し90歳で亡くなるが、それまで50年間は現場に立つことができず、ほとんどベッドの上で生活しながら執筆活動や後進の育成に尽力した。
ナイチンゲールがクリミア戦争からつなげた看護という学問の発展
しかし、そこは転んでもただでは起きないフロー。後遺症に苦しみながら、ベッドの上で座りながら精いっぱい取り組んだ仕事の遺産はすさまじい。彼女のベッドの側には訪問者が絶えず、日本からはあの津田梅子をはじめとする、時代を先駆けた女性たちが教えを請いに行っている。
まず、野戦病院での功績が讃えられてオスマン・トルコ皇帝とイギリス政府の両方からボーナスが出たので、それを使って後進育成のためナイチンゲール基金と看護学校を設立した。世界初の看護の専門知識を教える学校。
ここでは宗教に関係なく、看護の技術や病院の機能・管理にかんする理論と実践を学ぶことができる。ちなみに野戦病院のあったイスタンブールにもナイチンゲールの名前を冠した看護教育の機構がある。
さらに、劇中でも描かれていた医療統計学の円グラフ。野戦病院での入院患者数の推移や死因を分析した円グラフは、女王や軍部の上層など、医療現場にいなかった人や専門家ではない人にも理解できる。
ジョン・ホールのようなフローに足元を掬われた軍部の人間がグゥの音も出ないほど説得力のあるデータ。これを議会に提出し、英国陸軍の医療を大改革できた。
この功績により、フローは女性初の王立統計協会の会員となった。彼女は看護婦だけでなく一流の統計学者なのである。
実は、2階席で観劇した私は得をした。フローが生み出した円グラフがなんと、舞台の床一面にデザインされていた。「鳥のとさかグラフ」というらしいが、私達が小学校で教わるような蜘蛛の巣状のグラフではなく、円のパイが大きく飛び出ているところと小さく狭くなっているところが見える。
これをフローが発明し、ヴィクトリア女王の心をも動かしたのかと思うと感慨深い。舞台を高い位置から見下ろせるラッキーな席を取った方、是非チェックしてみてほしい。
ナイチンゲールに恋するボブのような患者が実際にいた?
重傷を負って天国に行きかけたところをフローに救われた若い兵士、ボブ。
そのおかげでグレイの姿も見えるようになり、いつも警戒している。だいぶ若く頼りなさげで、「ナイチンゲール様は僕がお守りします」とか言いながら、駆け付けるのがいつもちょっと遅い(苦笑)。
しかしラストシーンにも出てきて、フローの帰国後もずっとそばについて来て偉かったわね~とか思えてしまう、あのボブ。
彼は特定の人を表しているのではなさそう。どうも野戦病院にボブのような患者が何人かいたらしい。フローの看護があまりにも献身的だったために、患者たちの中には彼女にプロポーズする兵士もいたとのこと。
しかし彼女は看護に従事する前、長いこと好きだった男性をフっており、一生独身で仕事をすると決めていたようだ。
その逆に、医療する側が患者に対して恋愛感情を持ってしまうのがナイチンゲール症候群。なんだか、実際にフロー自身がそんなことなかったのを考えると不名誉な病名。しかし、献身的であればあるほど陥りがちな闇ということだろうか。
こんなところにも、献身というニュアンス的な意味で彼女の名前が使われている。
クリミア戦争で学んだ、「目先の援助だけではいけない」こと
今でも看護教育を受ける人のバイブルになっている『Notes On Nursing(看護覚え書き)』、看護の効果を最大にする病院機構を提唱した『Notes on Hospitals(病院覚え書き)』。フローの代表作である。
ミュージカルの劇中、クリミアの野戦病院を大掃除する場面でフローが「窓を開けて日の光と新鮮な空気を入れましょう」と歌っていたが、まさにこれだった。
明るい陽光と綺麗な景色を取り入れること、換気、静かな環境、ベッドの間隔、ベッドで食事ができるテーブル、ナースステーションの設置に至るまで。
彼女が提唱したものは、今では当たり前の病院建築や設備である。基本すぎて、かつてそれが当たり前でなかったことに誰も気づかないくらいだ。
傷病兵の手当だけではなく、衛生管理。
でも掃除だけでなく、根本的に病院機構から変えること。
看護の技術だけでなく、救うことを喜びとする心得を持つこと。
自分自身の仕事だけでなく、著書の出版や学校の創立による後進の育成をすること。
フローの考え方はいつもスケールが大きい。もちろん目の前の患者のケアは第一だが、木を見て森を見ずでは済まされない看護の問題を、俯瞰していたように思う。
すべての原点となったのは、裕福な両親とともに貧民へ施しをした体験だった。
目の前のお金や食べ物など必要なものを買い与えることはできる。しかし、それだけではずっと、目先の援助だけ。大切なのは彼らが貧しさから脱却すること。職業訓練として教養や技術を身につけたり、雇用を作り出したりすること。
『Notes on Pauperism(救貧覚え書き)』は、力強い言葉でこの考え方を訴えた彼女の著書。ネットで英語と日本語訳を読むことができる。
齧りだけ読ませていただいたが、フローの集大成と言えるのではないだろうか。看護を飛び出して、人を救うとはどういうことかを大局的に考えた傑作と思う。これが国際協力や社会福祉のバイブルになっているのも納得だった。
ミュージカルの最後は温かい涙があふれるような景色だった。ランプの貴婦人が円グラフの中心に佇み、天井にはまるで夜空の星々のように無数のランプの光が輝いていた。彼女の遺した膨大な功績と、彼女の背中を追い、今この瞬間も人を救っている膨大な後進たち。
ここに流れているのは、ジョン・ホールと対決し「私が消えてもきっと誰かが私の信じた道を歩む」と圧倒的な声で歌ったメロディ。
ランプの貴婦人は今も生きている。彼女が信じた道を、今日も誰かが歩んでいる。
終わりに
フェミニズム末期の時代に女子高で学んだ私が、こんなにナイチンゲールを追ったのは初めてでした。
なぜもっと早く彼女のことを研究しなかったのだろうと思うと悔やまれるくらい魅力あふれる女性であり、専門職、ビジネスパーソン、リーダーシップの側面からも刺激を受けました。
何より『救貧覚え書き』によって、人として誠実であることはどういうことかを突きつけられ、ハッとさせられました。彼女の著書を読みたい!と今は思えます。
その後でもう一度『ゴースト&レディ』を観たら、また違った感想を持てるかもしれません。
『ゴースト&レディ』ナイチンゲール語り前編はこちらからどうぞ。

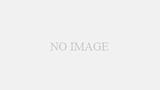
コメント