劇団四季オリジナルミュージカル『ゴースト&レディ』を語りまくるシリーズ第2弾。今回から2回にわたり、主人公フローレンス・ナイチンゲールの人生について紐解いていきます。本記事では看護との出会いからクリミア戦争まで。是非楽しんで最後までお読みください。
この作品、劇団四季がウェストエンドとブロードウェイに進出する作品としてふさわしいと本気で思っています。ナイチンゲールの話だから、様々な国の人が知っているネタ。歴史的背景も現代に通じる群像劇もメッセージが強い。制作陣も国際色豊か。違う国で応用が利かないわけない!
この作品が世界に進出する日が楽しみです。
『ゴースト&レディ』で描かれなかったクリミア戦争での大舞台前
看護に出会うまで
フローレンス・ナイチンゲール(以下、作品に倣ってフローと呼ばせてください)は両親が旅していたフィレンツェで生まれたので、フィレンツェの英語読みのフローレンスが名前になった。1820年生まれ、90歳で亡くなったので当時としてはものすごく長生きである。
看護を最初に志したのは22歳の時だが、その前の16歳で「神に仕えなさい」と神様から啓示を受けたとのこと。
そのエピソード、実はたまに聞く。ジャンヌ・ダルクもそうだし、修道院でシスターになる人は神からの啓示を受けたことを理由にする人がいる。私自身は神様を信じていないので理解しがたいが、どんな感じなのだろう。
フローの場合、ここで修道院を選ばなかった。神様の期待に応えるため自分にできることは何かを探し、看護の道を見つけるのだ。
ミュージカルでも男性の求婚を断った時、親と口論になった。「私は結婚よりも神の御心に応える」「(父)だったら修道院に行け!」「いいえ、祈りではなく行動に移す」と。
祈りにすがる性格でも、スピリチュアル好きでもなく、現実主義者だったことがうかがえる。修道院に閉じこもって清貧と祈りにすがっていても、社会は動かせないと考えていたようだ。
彼女の考え方の背景には豊かな学問があった。シリーズ第1弾にも書いたが、彼女は高等教育を受けており、特に数学や統計学が得意なリケジョだった。
着飾って人づきあいをし幸せな結婚をする社交界よりも、自分を高める方が面白いと気づいてしまったのだろう。そして両親が貧農に施しをするところへ同行したとき、劣悪な環境で暮らす貧民たちの惨状を目にし、「これだ」と看護の道に目覚めた。
幽霊に憑りつかれるほど絶望していたのか
はい、そうです。看護のキャリアを切り拓くまでは。
自分の生きる道を見つけたはいいものの、当時の看護婦は現代と全く違った。フローが何十年もかけて、看護の概念も労働環境も根本から覆すパイオニアとなった。
フローが目指した看護婦は、卑しい身分の女性がつく卑しい職業だった。
薄給なのに辛くて汚いからとか、そういうのではない。お酒にまみれ、たいした仕事もせず、むしろ患者とイヤラシい関係を持って風紀を乱す。なんでそんな給料泥棒も同然の仕事が罷り通っていたんだろうと不思議に思うくらいだ。
それを良家のお嬢様が本気で目指すなんて、周りから見ればどうかしている。
しかしフローは違った。この目で見た貧民や病人の惨状をどうかしなければ、神の期待に応えることなどできないと考えた。当然それを言っても家族は理解できないから、長い間ぶつかり合った。
好きだった男性(しかも理想的な結婚相手)も捨て、ほかの縁談もすべて蹴り、自宅軟禁のような扱いを受け、気が付くと31歳。生きるのをやめようと思うくらい精神は衰弱していた。
しかし、チャンスが訪れる。31歳でドイツの看護施設を訪問してから無理やり看護の訓練を受け始めた2年後、33歳にしてロンドンでの看護の仕事が舞い込んでくるのだ。
医者や学者が多く住む、ロンドンのハーレーストリート。あの『ジキルとハイド』のジキル博士も、映画『英国王のスピーチ』でジョージ6世の吃音を治した主治医も、ここに住んでいた。フローは家を飛び出し、このハーレーストリートにある「淑女病院」で総監督に就任する。
今もド定番のナースコールをここで発明。その後も次々と病院施設の改革を推し進め、あれよあれよという間にクリミア戦争へ。
ミュージカルでは「看護師」ではなく、ちゃんと「看護婦」と、当時の呼称が使われていたのが気持ちよかった。
現代の私達が使わなければいけない「看護師」という職業名は、1990年代で様々な職業が性別にかかわらず多くの人に開かれた時代に始まった。しかし19世紀、「看護婦」は女性の仕事だった。
フローが男性や旧式の社会やらと戦って作り上げた女性の誇り高き職業の名前を、現代の我々の物差しで勝手に変えてはならない。フローレンス・ナイチンゲールに対して「看護師」という呼び名を使うのはナンセンスだ。
そこをキッパリと区別した劇団四季の演出部の方々、本当にありがとうございます。
『ゴースト&レディ』の見せ場!クリミア戦争の従軍看護婦として
逆境でのリーダーシップ
フローが引き連れた38名の看護団。様々な背景を持つ女性たちだったから、もちろん団結できないときもあった。彼女らをまとめつつ、フローは看護婦たちを拒否する軍の幹部と、劣悪な病院の環境と戦った。ジャーナリストと大衆の感情に訴えて資金確保をするため本国と書類のやり取りもした。
看護団が働いた野戦病院は病院ではなく、収容所も同然だった。まずベッドがない。床にシーツを敷いているがボロボロのまま洗濯もしない。入院服などなく負傷者は軍服のまま。薬品も包帯もない。汚物は廊下まで溢れている。それが建物に染み込んで悪臭とバイキンを放っている。
こんな場所で、負傷者は治るどころか劣悪な衛生環境によって病気になり、患者の50%が亡くなる有り様だった。
現場を統括する軍医長官のジョン・ホールが、現場の状況を「好ましい」と本国に知らせていたため、問題が放置されていたのだった。保身のためとのことだが、それが後でバレる方が怖い結果になると考えなかったのか…なんにしろ、とんでもない。
ここでフローは有り金をはたき、徹底的に掃除を行い隣に洗濯小屋も建てた。また、食事の改善も行った。それまでは腐りかけた具材のスープが提供されていたが、一流シェフを呼んで個人個人の病状に合わせたあたたかい食事を出すようになった。
こうして眺めてみるだけでも大改革である。看護そのものというより、病院の機構を抜本的に変えたと言ってもいい。また、そこで働く看護団は38名。今の日本の学校なら1クラス分の大所帯だ。
彼女らのチームワークを保ちながら、一人一人が自分の仕事に責任感と使命感を持てるよう、まとめあげるのは労力を要したはず。
さらに軍の組織の妨害にもめげなかった。彼らのせいで看護団のモチベーションを絶やさないよう腐心したと思う。強いリーダーシップを発揮して人の尊敬を集めなければ成し得ないことだ。
医療統計学の祖
フローがそもそもクリミア戦争の野戦病院のことを知ったのはタイムズ紙だった。フローは現場の惨状を、やはりタイムズ紙を使って本国の人々に伝えた。大衆が病院の有り様とフローの思いを知ることができるよう、従軍記者に記事を書いてもらい、協力者や資金を集めた。
この活動の中に、ミュージカルでも描かれていた特筆すべきエピソードがある。フローが野戦病院の入院患者の死因を円グラフにしたのだ。こうすれば、傷病兵が本当は何が原因で亡くなっているのかを数字で分かりやすく示すことができる。
これはフローが新しく始めた、医療現場の様々な現状を図解して分析する手法。今では医療統計学と呼ばれる学問。グラフやレーダーチャートを使い、数字で表して図解する。
そうすれば、いわばパイの切れ方や棒の長さがパッと目で見えるから、「分かる人には分かる」のではなく誰でも理解できる。
こうして図と数字で示すことがモノを言った。この医療統計学により、当時の野戦病院での死因が負傷そのものより感染症ということが明確になった。
おかげで感染症の原因が汚水であることを突き止め、必要な対策が分かった。それを新聞で示したから支援も集まり、掃除や洗濯の環境を整えることができた。50%に上っていた野戦病院での死亡率は2%近くまで減ったらしい。
フローが発明した統計法による病院の環境分析は、もちろんどんな病院でも応用が利いた。
「誰も一人で逝かせない」
さらに、フローは回復せず最期を迎える兵士を看取り、遺族にもお悔やみの手紙を書いたとのこと。
上官が部下の戦死を家族に手紙で伝えるというのは聞いたことがあるが、それならきっと、亡くなった部下がどんなに勇敢だったかを讃えたり、どこで亡くなったかを報告する内容だろう。
しかし看護婦は病院でゆっくりと話をしたり、痛みに耐える姿を見たり、最後に家族に言い残した言葉を聞く。それを手紙で遺族に伝えたら、上官の手紙とは全く違う内容になる。
遺族にとっては、遠い戦地で亡くなった家族の様子は1行でも多く知りたい。そんな願いを叶えてくれたのがフローの手紙だったに違いない。
劇中でフローは「誰も一人で逝かせない」と言っていた。病院に入れられた兵士の中には重症患者もおり、とても全員を救うことはできない。けれど汚物にまみれ孤独に逝かせることだけは絶対にしない。体を洗い、清潔なベッドで、眠るまで優しい眼で手を握っていることはできる。
フローは信心深かったようで、そもそも看護を志したのも神の啓示を受けたからだった。看護団の中にもシスターがいた。
その信心深さに加えて、なんと心理学も勉強したことがあったという。人がどんな時にどんな気持ちになるか、慮る能力があった。だから患者や遺族の心のケアまで気を遣うことができたのであろう。
こうした心のケアも、現代の看護において大切な側面になっているのは誰もが知るところである。
終わりに
本当はナイチンゲールについては1つの記事で終わらせるつもりでした。しかし語ることが多すぎてクリミア戦争から帰国した後については次の記事にしないと、しっかりと彼女の人生を追うことができません。
初めてナイチンゲールという女性を紐解くと、なんで今まで注目しなかったのだろうというくらい尊敬の念でいっぱいです。後編も心を込めて執筆いたしましたので、こちらから是非どうぞ!

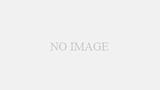
コメント