2025年1月日本初演『SIX THE MUSICAL』シリーズ第5弾。
この記事ではヘンリー8世の4番目の王妃、アン・オブ・クレーヴズを特集します。
いつもの通り、アンの持ち歌に翻訳をつけ、歌の内容から見える彼女の人生を紐解きます。
「ハウズ・オブ・ホルバイン」って何?
離婚させられたけれど、その後は?
400年前に生きたアンと現代の女子との共通点が分かる?
どうぞ最後までお楽しみください!
アン・オブ・クレーヴズの持ち歌「ハウス・オブ・ホルバイン」【翻訳】
アン・オブ・クレーヴズ:
ホルバインの家へようこそ
やった!いいね!
ハンス・ホルバインは世界に名を馳せる
美女なら誰でも絵に描く
スペインからフランスまで
ドイツもね
王はそこから一人を選ぶ
でも誰になるのかな?
コルセットをつけて
ベルトを締めて
ウエストは9インチ以上あっちゃダメ
化粧品に鉛の毒があるから何?
少なくとも顔色が良ければ男が寄ってくるわけでしょ
恐怖を無視しよう それで大丈夫
恐れなんかなかったことにするの
だから「はい」はOK 「いいえ」はダメ!
だってあなたは今ここにいるんだから
ハウス・オブ・ホルバイン!
やった!いいね!
ハウス・オブ・ホルバイン
ホルバインに肖像画を描いてもらうなら
お姫様は美しくいなきゃ
一番素晴らしい発明は
みんなを映(ば)えさせることなんだから
そう!素敵だよね
髪をもっと金髪に見せるなら
膀胱で作った魔法の素材を加えちゃうの
このヒールを履けば 背が高くてセクシーになる
40歳まで歩けるか保証はできないけどね
恐怖を無視しよう それで大丈夫
恐れなんかなかったことにするの
だから「はい」はOK 「いいえ」はダメ!
だってあなたは今ここにいるんだから
ハウス・オブ・ホルバイン!
やった!いいね!
ハウス・オブ・ホルバイン
歌から見える「モテ」への皮肉
ちょっとドイツ語の解説
この歌はアン・オブ・クレーヴズがドイツ出身という背景から、ドイツ語が所々に使われている。それらは日本語で雰囲気と意味が通じるように意訳した。
そもそも「ハウス・オブ・ホルバイン」とはヘンリー8世お付きの画家ハンス・ホルバインをもじっており、Haus(ハウス)は発音の通り「家」。画家のアトリエの名前として考えれば妥当。
レディー・ガガのクリエイティブチームがHaus of Gagaと呼ばれていることから発想を得たのではないかと言われているが定かではない。
2行目の「やった!いいね!」について、「やった!」はドイツ語でJa。英語でYea, oh yea! のような掛け声として使われている。「いいね」のdans ist gutは日本語にすると「それ、いいね」となる。
「ハウス・オブ・ホルバイン」を現代のソーシャルメディアで「いいね」をつけるような感じで解釈が可能ではないだろうか。
続いて「恐れなんかなかったことにするの」の箇所はWe’ll turn this vier into a nineとなっている。Vierは「4」。アン・オブ・クレーヴズが4番目の妻で、「9人分の役割を担ってやるわ!」みたいな意味にとれないこともない。
しかしvier(ドイツ語)はfear(英語の「恐れ」)と同じ発音、nine(英語)はnein(ドイツ語で「いいえ」)と同じ発音。紛らわしいったらありゃしないが、ドイツ語と英語で発音が同じ単語と、意味との掛け合わせで遊んだ箇所である。
アイドル風の翻訳と恐ろしい「映え絵」
曲を聞くとすぐに分かるが、曲調も歌い方も「ヤァ!」という掛け声も、めちゃくちゃアイドルっぽい。AKBやらモー娘やらと同じノリだ。気持ち悪いオタク男がメガネとハチマキとペンライトで踊り狂っていそうな曲。
したがって翻訳も今までで一番フェミニンで子供っぽく、10代の少女が精いっぱい可愛く演じているような言葉遣いをあてている。強い女風でもギャル風でもなく、アイドル風がこの曲には合っている気がする。
内容は、だいぶ恐ろしい。
ヘンリー8世へ贈られるお見合い写真代わりの肖像画をホルバインに書いてもらう時は、実物の2倍は盛らないといけないようだ。
現代なら「映え写真」だが、当時は肖像画なので皮肉を込めて「映え絵(ばええ)」とでも言うべきか。
つまり、プリクラ。インスタ。加工に加工を重ね、デートで待ち合わせしても本人だと気づかないマッチングアプリのプロフィール写真。洗顔した後で別人に変身する詐欺メイク。
ウエストが9インチ=22.86cm。…いや待って、内臓どこ行った?さすがにあり得ないよね?あ、そうか。実際のウエストに関係なく画家に注文したのね。
顔に塗る化粧品に鉛…触れすぎたり粉を吸ったりしすぎると、発達障害や認知障害を引き起こす恐ろしい毒になるらしい。なんで鉛にしたんだろ?
金髪をより映えさせるために塗るのは、そう。膀胱で作った液体らしい。ニオイもバイキンもすさまじい!!
無理して可愛くするのは400年前も現代も一緒
男のために危険を冒して自らを盛りに盛る女性。アン・オブ・クレーヴズをはじめ、当時の女性たちを笑うことなんてできない。現代の私達も似たようなことをしたこと、あるよね。
寒いのを我慢して体のラインや脚の細さが分かるように薄着したり、歩くだけで腰や膝にダメージを与える高すぎるヒールや、転べば骨折するレベルの厚底靴を履いたり。
女性は古今東西、多かれ少なかれ、男性に気に入られる努力をしてきた。ちょっとくらい危険でも男性の目を引くならと。
自然体でこそ云々かんぬん~というのは、もっと年齢や経験を重ねた人。もしくは可愛く作らなくても相手が見つかったラッキーすぎる人。中身に惹かれる男性に出会えた人。
この曲は、そうして男性のために無理して危険を冒す女性の努力を思いきり皮肉っている。
その努力が報われる確率は、まず狙った男性に伝わるかどうか、長期的に続く愛情になるかどうか、どちらの点を考えても非常に危ういのだから。
アン・オブ・クレーヴズの人生は大して不幸ではなかった
肖像画だけで婚約し、実物を見せた途端に何かがバレた
なぜこんな皮肉を歌うのかと言うと、アンはホルバインが描いた肖像画でヘンリー8世に見初められ、遠距離婚約し、実物を見た途端に離婚させられたからだ。
ジェーン・シーモア亡き後、ドイツとの政治的な友好関係を保つためにプロテスタントの女性との政略結婚を目論見ていたヘンリー8世はアンの肖像画を見て「はい、可愛い。婚約成立」とした。実物を見ずに。
しかし実物のアンと面会し、数時間を一緒に過ごしたヘンリー8世はその後、政略結婚を進めてきた側近に「ねえ、なんとか結婚ナシできないの?」と泣きついた。
結局その時は正当な理由が見つからなかったので結婚したが、1540年1月に結婚して半年後の6月には離婚してしまった。もうカトリックから独立しているので離婚は自由にできるのだ。
それにしてもヘンリー8世、実物のアンがそんなにショックだったのだろうか。
見た目だけ?鉛を使った化粧があまりにも厚かったとか?お化粧をとってビックリしたとか?それとも数時間を共に過ごす間、金髪に見せる素材が臭ったとか?もしくはマナーや話し方?
実際、婚約した当時のアンはドイツ語しか話せなかった。しかしそうして言葉が通じない相手と政略結婚するのは16世紀よりも前だってあったのだから、これから勉強すればよい話。
ひとつ考えられるのは、ヘンリーは学問とダンスが好きだったけれどアンは高等教育やダンスのレッスンを受けたことがなかったこと。
ドイツでの女子教育はイングランドとは違う。アンはドイツ語の読み書きと刺繍が得意で、キャサリン・オブ・アラゴンやアン・ブーリンの得意分野は知らなかった。
趣味や学問の話が全然合わないという理由での破局は、あり得る。会話がトンチンカンだったり、価値観がイングランドと違ったりすると、王妃として国をまとめる立場としても困る。
どれが本当の理由かは憶測の域を出ない。いずれにせよ、数時間でアンの人となりを観察したヘンリーは、よほど「ダメだこりゃ」と思う何かを見てしまったのだろう。
離婚後はむしろ悠々自適
アンは離婚してもイングランド国内にとどまり、なんとヘンリー8世の「妹」として王族の待遇を受けた。つまり、貴族よりも上。2度目の結婚ももうしないで良しとされ、年金で悠々自適な生活を楽しんだ。
ヘンリー8世の6人の妻の中で最も長生きし、人生もいちばん自由で幸せだった人物とされている。
ヘンリー8世と6番目の妻キャサリン・パーの結婚式にも出ている。メアリー1世やエリザベス1世とも仲良くした。イングランドで余生を送ったので英語もペラペラになった。
なるほど、経済的な心配もなく自由に好きなことをして暮らせるセレブリティ。王妃としての義務を果たすため、やれ子供を産めだの国民に慕われろだのの重荷を背負うよりもよほど気楽じゃないか。
ヘンリー8世がカトリックから独立し、離婚OKにしたおかげ…とも言える。キャサリン・オブ・アラゴンの犠牲の上に成り立ったラッキーとも言える。
最後に
いかがでしたか?男性のためにする女性の努力を皮肉る歌が、強くて芯のある女性の雰囲気ではなくアイドルソング風。痛快なほどに風刺が効いています。見下げているのではなく、「女性の皆さん、大変よね」みたいな。
離婚はしたけれど大して不幸にはならずラッキーな人だった、という評価が一般的ですが、個人的にはやはり、自由気ままに見えてパートナーくらい欲しかったとか、子供が欲しかったとか、叶わなかった夢はそれなりにあるのでは?と思えます。でもそんな秘めた思い、どこにも書かれていません。
次回は5人目の妻、キャサリン・ハワードを特集します。乞うご期待!

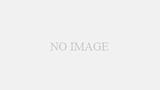
コメント