2024年お正月に日本を沸かせた新作日本オリジナルミュージカル『イサボー』、Blu-ray & DVDも発売されています。
今回はあらすじと登場人物をマニア語り。ミュージカルの中で触れられていたあんな場面、こんな場面は本当にあったのか?イザボー最大の失政トロワ条約の意義は、理解できているのか?
作家の桐生操氏による著書『血まみれの中世王妃 イザボー・ド・バヴィエール』をもとに解説していきます。最後まで是非お楽しみください!
ミュージカル描かれた歴史(史実)の背景
シャルル6世とイザベル(イザボー)が結婚したとき
ブルゴーニュのおじさま、ことブルゴーニュ公フィリップに連れられて顔も知らないフランス国王陛下シャルル6世に会いに来たイザベル。生まれ故郷のドイツではエリーザベト・フォン・バイエルン、イザベルはフランス語の発音。
ちなみに、なぜブルゴーニュ公フィリップがイザベルとシャルル6世の政略結婚を仲立ちしたかと言うと、彼の娘や息子がイザベルの親戚と婚姻関係にあったからだ。
ブルゴーニュ公領を確保するため、バイエルンの貴族と自分の子供たちをくっつけて親交を深めていたブルゴーニュ公は、バイエルン人からフランス王妃も探していた。そこでイザベルの叔父をとおしてイザベルを紹介されたのだ。
ミュージカルでは出会ったその場で結婚を申し込んでしまった若いシャルル6世。客席から「ロミジュリより早いちゅうねん!」と総ツッコミを入れられる展開だが、その好意を受けてイザベルも結婚を決断した。フィリップもめっちゃ喜んでいた。
桐生氏の著書にはその様子が詳しく書かれている。シャルル6世はイザベルに会う前から眠れないほどウキウキしていた。そして会ったとき、その美しさをじーっと見つめた。
その場は会見だけだったしイザベルもフランス語が分からなかったので会話はできなかったが、もうシャルル6世の心は決まっていた。
で、お見合いが行われたアミアンからアラスへ移動して挙式しようということになったのだが、陛下は待ちきれずにアミアンですぐ結婚式を行った。お見合いから結婚式まで、わずか3日。
噓みたいなホントの話。イザベルはシャルル6世の情熱に圧倒されたというか、もうこんなに愛されているのだからいいよね、という感じがする。不安はあったが嫌がったとは書かれていないし、結婚式も即位式も、その後の新婚生活も幸せいっぱいだったみたいだ。
シャルル6世と弟ルイの早駆け勝負
第2幕の最初に来るシャルル6世とルイのホッコリ兄弟エピソード。ラングドク地方に兄弟で旅をし、どちらが早く妻の元へ帰れるかの勝負で5000リーブルを賭けたという話。なんとこれも本当にあったアホな話。
歌の中に書かれたことがほぼそのまま、桐生氏の著書にも載っている。2人は別々の道を使って早駆けをし、三日三晩、一人の供も連れず、昼も夜も山や谷を越え、沼地を渡った。
勝ったのはルイだったが、負けてしまったシャルル6世をイザボーは温かく迎えたとのこと。ボロボロになって帰ってきた夫を介抱し、「おばかさんねぇ無茶して。でも嬉しいわ。うふっ」みたいなことを言いながら愛情を確かめ合った。
政略結婚ながらも2人が本当に愛し合っていたことはミュージカル全体でも深く描かれていたが、第2幕冒頭のこの楽しそうな兄弟はなんなの?と思えるくらい癒されるシーンだった。
これは実際、シャルル6世が発狂してしまう前にイザボーと愛で結ばれていたことを示す重要なエピソードだったのだ。
ブルゴーニュ公フィリップとオルレアン公ルイの政治的対立
ミュージカルの中でルイがイザボーに近づいたとき、ブルゴーニュのおじさまに妊娠マシン扱いされてメソメソ泣いていた彼女にオルレアン公ルイは「僕と叔父上は政治的に仲が悪くてね」ということを言った。その背景はかなり複雑で、それぞれが自分の野心のためにお互いを邪魔に思っていた。
ルイの奥さんヴァレンチーナはイタリアのミラノ公の娘なので、ルイはミラノ公の跡継ぎになれる権利を持っていた。そこでちょうど、ジェノヴァの貴族と民衆政府の対立があったのでルイが手を貸し、手柄を立てることでイタリアの統治者へ近づこうとしていた。
しかしジェノヴァはフランスとの重要な貿易中継地。そこをルイに盗られることはブルゴーニュの通商にとって大損害。
ブルゴーニュ公はジェノヴァの人々とシャルル6世に「ルイはミラノ公の企みでジェノヴァを支配しようとしていますよ~。ジェノヴァとミラノは敵対関係でしょ~いいんですか~?」と説得した。
ジェノヴァの人々の支持もあり、ブルゴーニュ公はルイからジェノヴァの統治権を奪って国王直属の統治下とした。これでルイがイタリアに領土を広げる夢がつぶれてしまった。
ローマ法王ボニファティウス8世がフランス国王フィリップ4世と対立し、アナーニ事件やら法王のアヴィニョン捕囚やら(世界史を習った人でないと聞き覚えがないと思いますがごめんなさい。そこを解説していると長すぎるので割愛)すったもんだの末、ローマとフランスのアヴィニョンに2人の違う法王がいるという状態になった。
この対立において、ブルゴーニュ公とパリ大学の神学者たちは、今の2人の法王を退位させて新しい1人の法王を選び、分裂を終わらせたいという立場だった。
対してルイは武力をもってアヴィニョン法王を正当な唯一の法王にしようとしていた。アヴィニョン法王がいればイタリア統治者への道をもう一度追うことができるからだ。
最初はパリ大学とブルゴーニュ公、フランス議会の勢力が優勢だった。しかし周辺国のアラゴンやスコットランドなどカトリック勢力がアヴィニョン法王を支持したり、ローマ法王がだいぶ権勢を取り戻してしまったりしたことから、協会は分裂したままに終わった。つまり、ルイの勝利である。
当時のドイツでは現役の皇帝を廃位し、新皇帝を選ぼうとしていた。
新皇帝の候補はイザボーの親戚、ヴィテルスバッハ家から。ブルゴーニュ公はもちろんこちら側。イザボーの実家とも仲良くしておきたいし、貿易の点でも有利だからだ。
対してルイは舅ミラノ公との関係から、現役皇帝の味方だった。
結果としては選帝侯の会議で現役皇帝が廃位され、ヴィテルスバッハ家の新皇帝が即位。まあその後はいろいろありすぎて割愛するが、ブルゴーニュ公の勝利とはいえ、ドイツとフランスの同盟関係は理想的な形で結論を出せなかった。
しかしその直後、最後に一触即発の事件がある。フランドルに滞在していたブルゴーニュ公のもとに、パリから知らせが届くのだ。ルイが国庫を横領して放蕩三昧し、自分に近しい人を政府の役人にしている。さらに国王の病状が悪化しているのに看病がろくにされていないと。
憤慨したブルゴーニュ公はパリ高等法院に「奴を止めんかい!国王を助けんかい!」と手紙を送った後、なんとパリへ進軍して威嚇。ルイはえらいこっちゃと反撃のため軍隊を編成し、もう少しで内戦というところまで行った。
イザボーの仲介と権力急上昇
ここで2人を止めたのが、ほかでもないイザボー王妃であった。内戦が起こればフランスが疲弊するだけだからと、ここで彼女はどちら側にもつかないことに決めた。そしてほかの公爵たちが同席する中で和解の儀式を取り仕切った。
そしてシャルル6世は、王妃に王侯貴族たちの小競り合いを仲介する権限を与えた。さらに新しい議会を発足させ、ミュージカルでは第1幕のクライマックスにあった勅令を発布する。
今後シャルル6世に狂気の発作が起こって政治ができないときは、王妃に議長権があること。シャルル6世が亡くなったときに皇太子が成人していないときはイザボーが摂政になること。
忘れてはいけないのが、この勅令はブルゴーニュ公フィリップが提案したということだ。
このとき、イザボーはブルゴーニュ公を信頼し、むしろルイを敵対視していた。争いには中立の立場を取ったが、イザボーは基本いつも、結婚の仲立ちをしてくれたブルゴーニュ派についていた。
フィリップはイザボーに決定権を持ってもらえれば、実際は自分が政治を思うままにできるから大丈夫。ルイが王弟だからと摂政になったり国王の座を奪ったりするよりずっと良かった。
したがって、王命の発布はミュージカルで描かれていたような、イザボーがルイを取り込んだ結果のクーデターではない。ルイの愛人になったのはフィリップがペストで急死してからだった。
トロワ条約とイザボーの晩年をもっと深掘り!
トロワ条約はフランスを売り払ったとされる理屈は百年戦争時代ならでは
イザボーを最悪の王妃たらしめる出来事がこの「忌まわしい」トロワ条約。娘カトリーヌがイングランド王リチャード3世に嫁ぎ、シャルル6世崩御の際はリチャード3世もしくはその息子にフランス王位継承権が渡るという内容である。そしてのちのシャルル7世が廃嫡される。
フランス王家・ヴァロワ朝の子ではなくイングランド王がフランスを継ぐということは、百年戦争の敵国に祖国を売り渡し、戦争には負けたという意味だ。
しかし、現代を生きる我々からするとこの理屈にはいくつかおかしいところがある。
だって、イングランドの王妃がフランス王家ってことでしょ?売り渡したというより、血筋が広がったってことだよね?むしろ婚姻によって和解できたってことじゃないの?
外国同士ではあるが同じ家計として仲良くそれぞれ統治しましょうよ、ていうハプスブルク家と同じじゃダメなの?
単純な疑問だ。そんな感覚を持ってもおかしくないのだ。
しかし百年戦争時代は違った。そもそも百年戦争の発端が、母方の血筋を理由にフランスをイングランドが取ろうとしたことだった。
フィリップ4世の皇太子たちが次々と死に、カペー朝が断絶。
そこでフィリップ4世の甥のヴァロワ伯がヴァロワ朝フランスの初代国王となった。
しかし、カペー朝フランス王フィリップ4世の王女を母に持つイングランド王エドワード3世が、つまりはフィリップ4世の孫ということで、我こそはフランス王位継承者だと主張したことだった。
これがきっかけで、フランス王家では女性の地位が徹底的に貶められた。
男性の地位は向上し、不倫や私生児もOK。しかし女性は妊娠マシンでしかなくなった。女性の血筋も政治的な役割も意味を持たなくなった。そして王家の男性の血筋を守るため、絶対に貞節は守らなければならないとされていた。
イザボーに「着飾って子供を産んでさえいればいい」と言ったブルゴーニュ公親子の発言は、我々からしたらトンデモナイが当時は常識的な考え方だった。
婚姻政策は、王位継承権から遠い人なら和解の条件として許容範囲だった。
事実、これ以前にも、30歳くらいのイングランド王リチャード2世(トロワ条約の時は次のリチャード3世)とたった7歳のイザボーの娘イザベルの結婚が、休戦の条件として行われた。
これができたのは、シャルル6世とイザボーの間にちゃんと男の皇太子がいたからである。
しかしトロワ条約はわけが違った。
トロワ条約でイザボーが娘をイングランド王に嫁がせたとき、フランスに皇太子はいなかった。イザボーの息子たちは次々と死に、たった一人残された息子のシャルル7世を廃嫡してしまったから。
つまり、現役のイングランド王がフランスの皇太子になった。シャルル6世が亡くなったらもうフランスはイングランドのものだった。
戦争中の価値観とはつくづく恐ろしい。百年戦争時代のフランスは母方の血筋を理由に侵略されることにトラウマがあったようで、女性を母親の役割に閉じ込め、それ以外の価値を否定した。でも平和を保つのではなく戦争を100年もしてしまった。
ちなみに、ラッキーなことにリチャード3世よりもシャルル6世の方がほんの少し長生きした。
シャルル6世が亡くなったとき、リチャード3世とカトリーヌの息子はまだヨチヨチ歩き。そんな幼児を王座につけるわけにはいかない。「俺、シャルル6世の息子ですから!フランスの皇太子いますから!」とシャルル7世がついに名乗りを上げたのである。
シャルル7世即位後のイザボー
ミュージカルの最後はイザボーとシャルル7世が和解した感動の名シーンだったが、これは物語の域を出ない。本当にこんな面会があったかもしれないが、分からない。歴史書に残されている記述はどんな感じだったのか。
桐生操氏の著書は当時の年代作家による一次資料を読み解いているが、イザボーがシャルル7世の戴冠式に参列したかどうかは一言も書かれていないようだ。イザボーはトロワ条約以降、完全に政治の場から去ってしまったからだ。
代わりに、ジャンヌ・ダルクがイングランドに処刑された後のエピソードがほんの少しある。シャルル7世がランスで戴冠式を済ませているにもかかわらず、フランス国内にはイングランドと同盟を組んでいる派閥があった。ブルゴーニュ派である。
そう、ブルゴーニュ公フィリップの息子ジャンはシャルル7世に殺された。だからシャルル7世はブルゴーニュ派の敵である。ジャンの息子フィリップ(おじいちゃんと同じ名前!紛らわしい!)はイングランドと組み、ジャンヌ・ダルクをイングランドに売った張本人である。
トロワ条約によってイングランド王兼フランス王になったヘンリー6世は、シャルル7世の戴冠に対抗しランスで即位式を行った。そしてヘンリー6世は、イザボーにしてみれば娘の子だから孫である。
パレードが行われた道に面した窓から、侍女と一緒に即位式を見物した。涙を流しながら。
そして最後に、シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ(ジャンの息子)が和解したとき。彼らはアラスで和解の条約を結び、フィリップはシャルル7世を正式なフランス国王として承認した。
これをもってトロワ条約は失効する。ヘンリー6世がフランス国王としての権利を放棄するのはそのずっと後だが、とにもかくにもシャルル7世は文句無し正当なフランス国王になった。
この知らせを聞いてイザボーはまた涙を流した。そしてその8日後に亡くなる。
歴史書はあくまで事実に基づいているので、イザボーの思いまで読み取ることはできない。でもフランスの息子シャルル7世とイングランドにいる孫ヘンリー6世、どちらも可愛い子に違いない。正直、どちらが王位を継ごうがイザボーの愛する子。
あとは権力とか国家とか、様々な社会背景に巻き込まれているだけのことだ。本当にどんな気持ちだったんだろうな、イザベル。
最後に
いかがでしたでしょうか?ミュージカルの物語に入りきらなかった歴史の裏側を知ることで、DVDや再演(切実希望!!)を100倍楽しめるはず。皆様もよろしければ、桐生操氏のご著書を読んでイザボーの時代を味わってみてください!

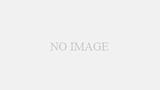
コメント