2024年7月、静岡市民文化会館に劇団四季の『キャッツ』が帰ってきた。2013年以来の11年ぶり。名古屋での千秋楽を迎え、まだまだ東海に旋風を巻き起こしている。
ジェリクル・キャッツたちに敬意を表し、小学3年生のころから20年以上本作ファンの筆者が、様々な視点で『キャッツ』を解説するシリーズ第1弾。
翻訳に当たって、珍しくちょっと長めの前書き
2020年に日本でも公開された映画版ミュージカル『キャッツ』の和訳歌詞(訳詞)があまりいい評価を受けていない。
無理もない。四季版を長年愛してきた人にとってはお気に入りの歌詞がなくて違和感を覚えるのも分かる。そこで、ミュージカルが大好きすぎて翻訳学の修士号を取りにイギリスへ渡った筆者が、ガチめに比較分析してみたい。
本記事ではグリザベラの歌う世紀の名曲「メモリー(Memory)」の訳詞を、劇団四季版と映画版とで比べてみた。
前半では英語歌詞の逐語訳ともつき合わせ、英語のニュアンスを読み取る。後半では、筆者が留学先で修めた翻訳学の理論を使い、訳詞の特徴を分析。最後までどうぞお楽しみください。
徹底比較!英語歌詞 VS 劇団四季版の訳詞 VS 映画版の訳詞
英語版の逐語訳
思い出よ
月明かりに顔を向け
思い出に導かれて
心を開き 行こう
そこで幸せの意味を見つけたなら
新しい人生が始まる
思い出よ
月明かりの中で一人きり
過ぎた日々を思えば笑みがこぼれる
私、美しかったわ
思い出せる
幸せが何かを知っていた あの頃
思い出よ よみがえれ
煙る日々の燃え残り
古びた冷たい朝の匂い
街灯は消え 夜が終わり
新しい夜明けが来る
日の光よ
日の出を待とう
新しい命を思おう
あきらめてはいけない
夜明けが来れば
この夜もまた思い出になる
そして新しい日が始まる
夏の木洩れ日
終わりなき仮面舞踏会
夜明けとともに
花びらのように思い出が散っていく
私に触れて
私を置き去りにするのはたやすい
思い出とともに独りきり
日の光の下にいた あの頃
私に触れれば 幸せが何かわかる
見て 新しい日が始まった
訳詞のルール ~口の動きに合わせる~
訳詞は逐語訳と重要視すべき点が全く違う。それもそのはず、観客が画面で読むのではなく、俳優さんが音に合わせて歌わなければならないからだ。すると、言語の正確さより芸術性が優先される。
そうなると、まずハリウッドやディズニーの訳詞を作る時には「画面の口の動きに合った音を入れる」という厳しい規定がある。口を動かして確認すると分かるが、「Let it go, let it go」が「ありの~ままの~」になったのが代表例。
その意味で言うと、本作はかなり高度にこの基準をクリアしている。長音で原詞と似た母音を使ったり、子音もほぼ同じ音を入れこんで、原詞の響きを活かしている。
特筆すべきは韻の踏み方。美しい韻が非常に目立ち、匠の技だと思った。
しかし残念だった点は、全体的にカタカナ語がそのまま使われている箇所が不自然なほど多かったこと。固有名詞のように扱われる単語はほぼカタカナ。「ビューティフル・ゴースト」と「アップ アップ アップ」までもカタカナなのは流石に手抜き感さえ覚えて顔面に縦線が入った。
「メモリー」でも「メモリー」と「デイライト」は四季版も映画版もそのまま。まあ、メモリーという単語は曲名にもなって象徴的であり、同じ音のデイライトも良しとしよう。
しかし映画版の「ムーンライト」、「サンライズ」、「タッチ・ミー」はいただけない。
カタカナ語だからこそ響きが良くなったり、スッと心に届く音ならいい。映画の中の歌はライヴパフォーマンスであり、読み返せないのだから、一瞬で腑に落ちる美しさと印象の強さがある言葉かどうかを第一に考えなければいけない。
カタカナ語が残っている3つの単語にその力があるかと言うと首をかしげる。言葉は誰もが知るかも知れないが、印象を頭の中で鮮やかに描けるまでに1秒以上かかるし、ムーンライト=月の光、サンライズ=日の出、タッチ・ミー=私に触れて、と美しい日本語が当てはまる。
なのに趣ある表現に訳せていない。いわば、安っぽさが否めない。
「タッチ・ミー」ってどう訳す?
これなんだよ問題は。たった3音。直後の It’s so easy to leave me の雰囲気を汲み取り、ガッチャンコして意味をとっても翻訳者はものすごく頭を抱える箇所だろう。「私に触れて、共にいて」という感じの一括りをどうまとめるか。
個人的には、四季版の「お願い 私に触って」も「ええ~?」だ。
まあ「私に触って」という日本語自体は合っている。文脈的に、肌が触れ合う意味と捉えるのが正しい。でも「触って」ってちょっと艶めかしすぎるというかバイキン扱いされてきたの?と聞きたくなる。「私に触れて」ならまだ手の感触が優しそうなのに…。
しかも、Touch me の3音(正直、2音ともいえる)に4文字の「お願い」を押し込むと、音が切れて響きの良さに支障が出る。
また、四季版は直後に「私を抱いて」で「触れる」という動きから伝わる温度をわずかに描く。映画では「変わらぬぬくもり ここにあるわ」とあり、こちらがより感動的に思える。
これだと猫を抱っこしたときの温度が思い浮かぶ人もいるかもしれない。が、四季の「光とともに」があるとOf my days in the sunをしっかり訳せている。
んで、オマエはどう訳すんじゃいと言われそうなので筆者の案も一応。口先だけの批判ではあまりに無責任なので。試しにTouch me ~ Of my days in the sun を合わせてこう訳してみようか。
「この手 あなたも触れて 失くしたぬくもり 蘇るわ」
やっぱり微妙だ。Touch meという英語を的確に日本語にできる方、我こそはという方、いませんか?
英語から日本語への訳詞に入る情報量は、原詞の1/3
そう。一般的には英語の原詞を日本語の訳詞に直すと、情報量は1/3に減ってしまうと言われている。
これが最難関。英語で同じような意味が繰り返されているなら1回にまとめたり、行をまたいで伝えたい一番大事なメッセージを要約したり、無駄な「てにをは」を極力減らしたり、日本語の語彙を慎重に選ばなければいけない。
でなければ訳詞は薄っぺらい言葉にしかなれない。
たとえば、4行目「Open up, enter in」。縦を横にするだけなら、一番簡単な言葉で「ひらいて、始めて」となる。簡易な言葉だからこそ「なんのこっちゃ」とならないように表現しなければいけない。したがって四季版も映画版も直前の「Let your memory lead you」と合わせている。
しかしこの曲で一番問題にしたいのは、それを気にしすぎて誤訳になったような箇所があること。 Like a flower as the dawn is breaking / The memory is fading の2行だ。
四季版と映画版とでは「花」だけ同じ。朝が開くか思い出が空に放たれるかの違いがある。
しかしここで注目したいのはfading (fade)という動詞との組み合わせ。To fadeの意味は「花びらが散る」、「徐々に消える」。つまり like a flower が the memory is fading と合わさるのではないか。
The memory is fading like a flower as the down is breaking
夜が明けるとともに思い出が花びらのように散っていく
こう理解するのが良いのではないだろうか。
字余り&字足らずと逆アクセントでリズムが悪い
おそらく映画を観た人がいちばん気持ち悪かったのはこれだと思う。
まず字余り&字足らず。1音に2音以上を押し込めたり、リズムを弾ませるために切ってある音を無理につなげたりすれば、せっかくの音の響きが損なわれる。「Memory」なら先程書いた「Touch me」(2音)を「お願い」(4音)と訳したのが字余りの状態。
単語の抑揚が不自然になっているせいで聞き取りにくい言葉は、作品全体で何か所も見られた。単語の抑揚とは、「うみ」が海になるか膿になるか、「あめ」が雨になるか飴ちゃんになるか等のこと。
抑揚が逆になっていると違和感があるばかりか、酷い時は意味を取り違え、映像の流れの速さに観客が付いていけなくなる。多少、単語を捏造しても抑揚が音に合う言葉を選ぶと、想像以上に効果が高くなる。
その効果がかえってリズムの良さ、英語の原詞の響きにソックリになるというならいい。しかし聞き取れない日本語になったり、原詞のリズムを壊したりすると途端に雰囲気が崩れる。心に「入ってこない」言葉になってしまう。
まず字余り・字足らずはできるだけ避けるべき。大切なのは、原詞のリズムをそのまま生かすことである。たとえば長音で延ばす1音は1音になるよう訳を当てる。また、息継ぎ(ブレス)の位置をそのまま残しておく。それらができると歌いやすさが格段に違う。
最後に
長すぎるのでこの辺で止めなければ。だいぶ辛口で申し訳ないが、そのくらい訳詞は難しい。正解もない。
しかし、突き詰めることはできる。俳優さんと観客の気持ちになって歌いやすさ・聞きやすさを考えられるか。英語の原詞が醸し出す芸術性どこまで再現できるか。
この記事をお読みになり、訳詞の学問に興味を持たれた方、是非コメント欄でお知らせください。

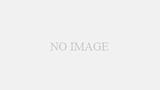
コメント