来ましたね、演劇ファン・ジブリファンの皆様。日本が満を持してウェストエンドに撃って出た宮崎駿の超大作『千と千尋の神隠し』。2022年の初演を配信でなんとか観た筆者が、様々な観点から本作を語ります。
アニメは見たけど舞台はちょっと…なんてお思いの、そこのあなた!侮らないでね!(by 中田さん笑)なぜ本作が日本最初のロンドン進出作品となったのか?アニメ版と舞台版の相違点は?舞台版ならではの見どころは?ぜひ最後まで楽しんでお読みください。
物語と台詞の変更点はほぼ皆無!
物語と台詞にかんしては、舞台版はアニメ版がまんま生身の人間になっただけです!
これはすごいことだ。原作とリメイク版で物語が変更されるのはよくある話だ。表現できる幅や得意分野が違うことを考慮したり、敢えてメッセージを変えることでオリジナリティを出したりする。
しかし本作は違う。よくもまぁこんな細部までと言いたくなるほど、台詞も場面の流れもアニメの世界がそっくりそのまま舞台上に再現されていた。
アニメに忠実すぎてビックリする点は例を挙げればキリがないが、我慢できないのでちょっとだけ書かせていただく。
冒頭の車に乗っている間に道が悪くなってくるところ
釜爺の天丼
イモリの黒焼き
腐れ神の臭気で腐る白ご飯
腐れ神の体から引っ張り出される自転車
千尋が釜爺の部屋から湯婆婆に会いに行く時のギャ~ピ~騒ぐ様子
エレベーターのレバー
そして何より、台詞の一つ一つが全く変更されていない。
著作権とかジブリと東宝の話し合いとか、大人の事情はあるかも知れない。しかし、演出家ジョン・ケアードの心意気が大きいのではないだろうか。
彼は『レ・ミゼラブル』の日本版も演出しており、日本人の現役俳優さんたちから厚い信頼を受けている。さらには奥様を日本からイギリスへお持ち帰りした親日家。彼が作品への愛と日本文化への敬意を持っているからこそ実現した、稀有な仕事だったと考えられる。
デジタルの時代に異世界を表現する、あえてアナログな神器たち
アニメで本作を見た人ならだれもが思うだろう。
あの不思議な魔法の世界をどう表現するの?
様々なサイズや見た目を持ち、透けたり空を飛んだりする神々をどう演じるの?
あの魔法の世界や神々を表現するなら、この時代だからプロジェクションマッピングとか使うんじゃない?
ノー。目立たない茶色の作務衣を着たダンサーさんや俳優さんが、大道具や小道具、人形、着ぐるみのような衣裳、そして体の動きだけで魔法を演じていた。
そう、すべてアナログ。巨大化するカオナシも、怒りを暴発させる湯婆婆も、ハク龍も、花も。なのに使っているものがまるで神器に見えるくらい見事な使いようだった。
演劇の世界は嘘の世界である。ノンフィクションと銘打たない限り、すべてが作り話。その中でリアルを追い求めるのが俳優さんや演出の仕事なのだが、嘘をもっと強調することで、嘘が現実よりも凄みをもって心に響くことがある。
書き方が難しいが、つまり、観客も演劇が嘘と百も承知しているからこそ、リアルではあり得ない世界を楽しませることが可能なのだ。
本作では、原作がアニメだからこそ映像のテクノロジーを一切使わず、アナログに徹底したことが逆に新しい。そして生身の人間が体全体を使って全てを表現するからこそ、チームワークで作り上げる生の舞台の鮮やかさがあった。
ほんの少しの歌で生身の人間の味わいを
舞台版だからこそアニメ版よりもグッと味わい深くできる演出が、歌である。本作はミュージカルではない。歌が台詞の延長上として使われないからだ。その代わり、場面の背景を描写するため、ほんの少し歌の力を借りる。
神々が列をなして温泉宿に来る曲は、物言わぬ神々が温泉で疲れをとるウキウキ感が満載。「神々は今日も世界を治めて膝は折れ、この湯屋で疲れを癒す。さあさあどうぞ」といった歌を女性たちが容器に歌う。
そう、映画を見た人なら想像できるだろう。あの曲に歌詞を付けたのである。面白そうでしょ?あなたも神々の列に並んで一緒に湯屋へ入りたくなるはず。
台詞のある役で唯一ソロ曲のある釜爺は、じいちゃんと「ほんの少し前まで娘だった」ばあちゃんに教わった人生訓を登場シーンで歌う。アニメでは語られなかった釜爺の深層が垣間見える。
そして第1幕の最後にソプラノで訥々と歌われる曲は情緒たっぷりに夜の海を走り抜ける電車の風景を歌い、癒し効果抜群。
釜爺以外、千尋やリン、湯婆婆など台詞のある役は一切歌わない。ジョン曰く、「歌は登場人物の心の奥を表現するツール。でも本作では台詞や動きにすべて出ているから歌う必要がない」とのこと。
原作のアニメを見てそう思ったから、新しい流れを作ったり台詞を変更したりするよりも、アニメを細部まで再現することを選んだのだ。納得の選択。
ダンスで舞台版ならではの華やかさをプラス
もうひとつ、舞台版の本作を彩る重要なパフォーマンスがある。ダンスだ。生身の人間がアニメで描かれる神秘的な世界を表現するには、ダンスはピッタリなのだ。
神々の不思議な動きや空を飛ぶシーン等はもちろん、父役がカオナシをもてなす場面ではご機嫌な宴の踊りがあった。ちなみに、父役は有名なダンサーで振付家の大澄賢也さん。
どうしてもご紹介したいダンスの名場面がある。第1幕ラストシーンの直前。腐れ神が温泉でゴミを落とし、気持ちよくお帰りになった場面。祝福の舞がアニメ版の何倍も華やかだった。千尋も湯屋の従業員たちも湯婆婆も、舞台の隅から隅までが喜びに満ちていた。
異世界に迷い込み、怖い思いをし、必死に働き、初めて何かを成し遂げた千尋。その満面の笑顔とハッピーダンス。そして湯婆婆がツカツカと千尋に歩み寄り、ガシッと抱きしめ労ってくれる。
あああ良かったね千尋…。ここまでどんなに大変だったか見てきたよ。この世界でやっと成功体験をしたんだ…なぁんて感情移入した筆者は、おにぎりの場面と同じくらい号泣。
アニメ版ではどうしても出せない、ダンスのパフォーマンスと湯婆婆の「間」の取り方があったからこそ生まれた、新たな名場面だった。
カオナシが踊ってる!!
特筆しておかなければいけないキャラクターがいる。みんな大好きカオナシだ。
いやもうビックリした。橋で初めて登場する時は普通に歩いているだけだが、千尋に宿へと招き入れられる直前、グニャグニャと邪悪な気配をまとわせてカオナシが踊り出す。
めちゃくちゃいい。
カエルを飲み込んでからはカエル役の俳優さんでお笑い芸人の「おばたのお兄さん」がカオナシの声を演じるが、それ以外は一言も台詞がない。アニメで見られる「あ…」もない。その代わり、すべてダンスで表現する。
化け物の雰囲気、滑らかで気持ちの悪い手足が、カオナシの「触らなければ害はないのに刺激すると発揮される恐ろしさ」を滲ませている。
そしてカーテンコール。カオナシのお面を取った下から現れたのは、なななんと、綺麗なお姉さん。おーまいがー!男性のダンサーさんとダブルキャストであるが、劇場がどよめくのが映像からも伝わってきた。
カオナシはアニメ版でも個性際立ちメッセージ性も強いキャラクターだったが、ダンスという要素によって神秘性が増大した。舞台版の演出の妙に心から拍手を送りたい。
なぜ日本演劇界ロンドン進出最初の作品が『千と千尋の神隠し』なのか
これに関しては考えられる理由が山ほどあるし、筆者より原作に対して深い見識を持っている方々がいらっしゃるだろう。
本作はベルリン国際映画祭の金熊賞やアカデミー賞など、国内外で名誉ある評価を受けている。したがって海外での評判はお墨付き。
「手ぇ出したら終いまでやれ」
「挨拶したのかい?世話になったんだろ」
「自分の名前を大事にね」
などといった道徳を問うような名言もあれば、千尋がおにぎりを頬張って号泣する場面、腐れ神の体から引っ張り出された大量のゴミによって環境破壊に気付かせる場面、ハクの名前を思い出させる場面、豚に変えられた両親を見事に見分ける場面など、感動を誘う場面も多数。
これらすべてが宗教も人種も関係なく、大切なメッセージとして世界に通じるものばかり。
さらに、本作は英語で上演はできない。日本語の柔らかな響きがなければ本作の味わいは出せない。だから翻訳劇として海外のプロダクションに委ねるのではなく、海外においても日本人のカンパニーが日本語を使って演じなければダメなのだ。
タンゴやビートルズを日本語で歌うと雰囲気を壊すのと同じである。
この2つの側面を考えると、日本人による世界中の人々のための演劇で、これほどふさわしい作品はない。映像と生身の違いを乗り越えて、よくぞ舞台化してくれた。本作が再演を重ね、やがてロンドンだけでなく世界中の劇場でツアーになることを願ってやまない。

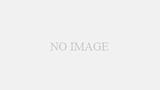
コメント