ミュージカル『天使にラブ・ソングを』の魅力を語るシリーズ第2弾。この作品がこんなにも愛される理由として、あらすじの濃さと双璧をなすのが音楽の素晴らしさ。様々な資料をもとに、作曲家と作詞家の紹介、曲の特徴や時代背景にも触れる。
そして筆者の経験談から、観劇中に見逃さないでほしいポイントを解説してみたい。最後までお読みいただければ、きっと観劇前の良い予習になるはず!
『天使にラブ・ソングを』を手掛けたミュージカル音楽界の巨匠たち
映画では既成の曲が使われたが、ミュージカル版『天使にラブ・ソングを』は全曲書き下ろし。2011年の第65回トニー賞にノミネートされている。
作詞作曲の2人はグレン・スレイター(Glenn Slater)とアラン・メンケン(Alan Menken)。2人はブロードウェイ版『リトルマーメイド』でもタッグを組んだ。
スレイターは他に『塔の上のラプンツェル』『ラブ・ネバー・ダイズ』『スクール・オブ・ロック』の作詞、メンケンは『美女と野獣』『アラジン』『ムーラン』『ノートルダムの鐘』など多くのディズニーアニメの作曲を手掛けている 。
とにかく何度聞いても飽きない。不思議だなと思ってはいたのだが、その理由は思わずダンスしたくなるリズミカルな音楽と、そこに付随する幸せな空気感が根底にあるおかげである。
そしてフィリー・ソウル、女子修道院らしい神聖な感じの曲、ミュージカルっぽい芝居曲の3種類が入り乱れている。歌詞もイキでウィットに富んだものから自分に重ね合わせて泣けるものまで、1作品の中で実に多種多様なのだ。
この時代、この場所ならフィリー・ソウルでしょ!
ぶちかますディスコ音楽
アラン・メンケンはミュージカル版『天使にラブ・ソングを』の時代設定が1970年代のフィラデルフィアと聞いて、「金脈を探し当てた気分だった」と語る。ズバリこの時代、この場所といえば「フィリー・ソウル (Philly Soul)」を狙い打てばいいからだ。
ソウル・ミュージックの1つで、アフリカ系のデロリスやエディが歌うならこれしかない。ディスコ音楽の先駆けにもなったノリノリのアップテンポで観客を乗せることもできる。管楽器や金管楽器などオーケストラが演奏するのにもピッタリ。
事実、初っ端からぶっ飛ばす。みんなに「塩ちゃん」と呼ばれている名物ミュージカル指揮者の塩田明弘さんが「ワン・ツー・スリー!」と軽快な声をかけたと思うと、トランペットが第一声からフォルテッシモで飛び出し、打楽器がリズムを刻み、ストリングスがものすごい速弾きで踊り出す。
前奏が盛り上がるとキラキラなカーテンの向こうから、デロリスとコーラスが現れる。
日本語版はコロナ騒ぎが始まる直前の2020年新年頃まで3回目の再演と、コロナ禍がやっと収束し始めた頃に4回目の再演があった。コロナ禍でぜんぜんミュージカルができなかった時期を乗り越えて、デロリスが舞台に帰ってきてくれた…
なんてありがたいんだ。登場シーンだけで涙がボロボロ流れるほどだった。そのくらい女神に見えてしまった。
サタデーナイトフィーバー好きが大興奮!?
シリーズ第1弾にも書いたが、エディのソロ曲「I Could Be That Guy」はトラボルタを狙い打っている。男声ファルセットもフェイクもあり、いかにもブラック・ミュージック。
それを歌いこなせば日本人の俳優さんでも現地のアフリカ系の歌手に見えてくる。ガッツリ芝居歌なのにディスコで流れていてもちっともおかしくない。
第2幕の最初には、デロリスの指導によって徐々に歌に慣れてきたシスターたちがミサを行うシーンがあるが、「サタデーナイトフィーバー」をもじって「サンデーモーニングフィーバー」。日曜日の朝に行うミサでディスコのフィーバー。
神様への愛やら聖書に登場する使徒やらを紹介しながら、シスターたちも神父様もギラギラの衣裳で弾けまくっている。実に愉快。映画『サタデーナイトフィーバー』を知っている人ならピンと来る音が入り込んでいる。
ほかにも作品全体にディスコ音楽が散りばめられ、もう楽しくって仕方ない。客席で踊り出しそうになるのを堪えなければいけない。私は『サタデーナイトフィーバー』を見たことがないが、詳しい人はこの作品との繋がりをもっと深掘りできるのではないだろうか?比べてみるときっと面白い。
修道女たちの聖なる音とディスコ音楽の融合
12回観劇して12回とも泣いた曲たち
ミュージカル版『天使にラブ・ソングを』の音楽で最大の魅力は、リズミカルなディスコ音楽と宗教音楽のような神聖な音が混在する芝居歌だと思っている。
まず、第1幕でシスターたちの歌がどんどん上手くなっていく「Raise Your Voice」。デロリスの指導によって、蚊の鳴くような声でしか歌えなかったシスターたちが音階を覚え、声を高らかにし、美しくハモッていく。
しきたりでがんじがらめだったシスターたちが、まるで新しい世界を発見したように目を輝かせていく。ここはたまらない。楽しすぎて号泣できる唯一無二の曲。
さらに第2幕、デロリスとエディとのキュン死しそうなシーンの後、「Look at Me」から「Sister Act」へ続く場面。もう一度スターを目指すと決めたはずが、デロリスの頭にシスターたちの声が響く。
無理やり掻き消して理想のディスコ・クイーンを思い描いても、清らかな歌声が割って入ってくる。ずっと夢見ていたことと、本当に愛している場所の食い違いにうろたえ、目指すべきものに気づく。ここも共感できすぎて号泣。
さらにさらに、第1幕ラストでは歌が上手くなった聖歌隊のシスターたちによるミサが初めて行われ、デロリスが作った曲「Take Me to Heaven」を歌う。
天国へ連れてって。マフィアの愛人であるデロリスが男を喜ばせるために歌う時と、シスターが神様のために歌う時とで意味が異なるのはお分かりだろう。これが、デロリスが1人+コーラス2人のバージョンと聖歌隊とで「うっひゃー」というくらい大変身する。
エレキギターの使い方が全然違うし、シスターのチビソロもあったり、その間に修道院長様などの登場人物の台詞が挟まれたり。
見事すぎる。シスターたちの弾けっぷりが愛おしくて、本来ならキャーキャーはしゃいでもいいのだが涙が止まらない。
ミュージカル好きではない人もアラン・メンケンの芝居歌は親しめるはず!
これはアラン・メンケンの得意技と言えるかもしれない。彼が書いたディズニーミュージカル曲でヒットしているものは、どれも1曲単体で歌えるものばかり。
その中で思い出してみれば、ただ立って歌うだけではなく物語が流れつつ歌われる曲がある。『アラジン』の「Friend Like Me」や「Prince Ali」、『美女と野獣』の「Be Our Guest」、『ノートルダムの鐘』の「Esmeralda」。どれもこれも、いわゆる芝居歌である。
ミュージカル好きではない人はよく、しゃべりながら突然歌い出すのが不自然とか、全編歌で物語を流すことに違和感があるとか言う。
しかし、そんな人でもアラン・メンケンの書いたディズニーアニメは楽しく見られるだろう。楽しく見たことがあるはずだ。それくらい、アラン・メンケンの芝居歌は物語や場面にスッと馴染む。
どんな理論を使っているのかは素人なので分からない。しかし彼の芝居歌のおかげで、このミュージカル版『天使にラブ・ソングを』はきっと、ミュージカルを観たことがない人にも「なんて楽しいんだ!」と思ってもらえると信じている。
この記事をお読みの皆様、ぜひとも日本語版6回目の再演を待ちましょう!

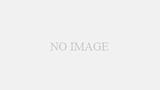
コメント