東宝ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』初日延期のニュースにファンは怒り心頭。延期の直接原因は「準備が間に合わなかった」というコメントだが、だったらそんなていたらくを許したプロダクション側の背景は?
そこには根本から原因を考え、解決しなければならない大きな問題が見えてくる。東宝だけでなく日本のミュージカルというビジネスが抱える労働問題を読み解きつつ、俳優さんの労働環境についても紹介する。ぜひ最後までどうぞ。
根本原因は東宝演劇の老害
謝罪文によると、延期の理由は準備が間に合わなかったのだということ。そして、東宝ミュージカルでは過去にも『千と千尋の神隠し』や『のだめカンタービレ』のゲネプロでトラブルがあり、その2作品はぎりぎり間に合ったが危なかったとのこと。
この問題は文字面より根が深い。日本ミュージカル界の労働問題と東宝演劇という古の大企業が抱える老害が絡んでいる。東宝は日本のミュージカル界で頭一つ抜きんでた老舗だが、私個人の印象で言えば、だから悪い意味で偉そうな会社だ。
いろいろな理由があるが、ファンとしてもはらわたが煮えくりかえるような思いをした経験が何度かある。
つまり、権威主義。理不尽な利益追求主義。積んできた学問の専門性よりも若さを重視するあたり、日本の伝統的な財閥に似ている。これが東宝演劇の闇の側面だ。
致命的な危機管理能力のなさ
今回の事件で痛感した。東宝が抱える大きな問題は、危機管理能力の低さである。だって今までに延期未遂が2回、今回とうとう…なのだから。
とうとうじゃないよ。未遂が2回もあったなら学びなよ。特殊な演出がある時はリハーサル期間を長くとらないと危険だということくらい、予測がついたはず。いや予測しなければいけない。
もし予測していながら「でも今までの2回はなんとかなったんだから大丈夫!」と判断したなら、それは企業の危機管理として間違っている。「あんなギリギリを繰り返さないためにはどうすればよいか」に転じなければいけなかった。
学ばなかったのなら、根本原因とそれに対する追究を怠ったということだ。時代の先端を走ろうとしている企業なら、危機管理のPDCAとして定番があるはず。
①「ただ一つの根本原因」を特定すること、
②目下でどのように対処したか、
③今後それを防止するには中長期的にどう対策を打てばいいか。
このあたりの常識を実践せず、ただただ作品を量産するだけだったのなら、デカい面さげて老舗企業を名乗ることなんてできない。
日本人の勤勉さとド根性精神など綺麗ごとに過ぎない。幹部たちが振りかざす昭和な指針を強要されるのは、現場で働く俳優さんとスタッフさんなのだから。
世界一短い日本ミュージカルの舞台稽古
そもそも日本のミュージカル界は、世界で最も稽古期間、特に舞台稽古の期間が短い。海外の演出家が日本版を担当すると「信じられない」と言われるそうだ。
具体的に比べてみれば一目瞭然である。
ブロードウェイとウェストエンドでは、稽古期間は6~8週間。作品の特徴を十分に考えて、必要だと思えば10週間取ることもあるらしい。そして舞台での通し稽古は初日の2日前にやるべきというのがスタンダート。
最初は非公開だから、不具合があっても大丈夫。初日までの2日間があれば最低1日1回は舞台で通せるということだから、調整が可能なのだ。最終通し稽古では関係者やプレスに公開できる。
もっと言えば、ブロードウェイやウェストエンドの新作にはプレミアというものがある。一度完成させた作品を「試しに公演してみる」という、お客様の前での実験。そこで観客の反応を見たり、演出家が実際に客席で見て違和感があった場面の演出を変更することができる。
それだけ作品をじっくりと育てていけるということである。
一方、日本では稽古場の稽古期間は米英と大して変わらないが、やはり短め。驚くのは、舞台での通し稽古をたった1回、ダブルキャストなら1人1回ずつの2回しかやらず、最初から関係者やプレスに公開する。ゲネプロと呼ばれるが、これを初日前日もしくは当日の昼に行う。
ギリギリが普通になっているのだ。実際の舞台上で本番の前に1回しか通さないなんて、素人の我々が考えても恐ろしい。
逆になぜ今までできていたんだろう。もう2~3日欲しいと、声を上げた人は今まで一人もいなかったのだろうか。労働組合がないから不満を言えばたちまち首?だから上の指針に逆らえる人がいない?
華やかに見える俳優さんの労働環境は想像以上に辛いのかもしれない。
俳優さんとスタッフさんの体調が心配
海外の翻訳ミュージカルばかりを企画し、違うカンパニーが稽古場と劇場を一定期間借りて、いわば家賃を払いながら上演するのだから、家賃を払う期間を短くしたい気持ちは分からないでもない。しかしそれは様々な点で労働者であるスタッフさんと俳優さんを搾取している。
1点目に、日本のミュージカル界は、俳優さんのお給料の基準は1ステージいくら(井上芳雄著『ミュージカル俳優という仕事』、2015年)。稽古期間のお給料は出ない。これこそが稽古期間の短さの原因になっている。
日数が少ない分、夜遅くまで働くスタッフさんだって多いだろう。俳優さんも短い期間で頭にすべてを詰め込まなければいけない。第一、稽古だって時間を拘束されているのだから労働の一部だと見なされないのはおかしくないか?
2点目に、英米では1週間8ステージしか上演してはいけないことになっているが(マチネとソワレ両方ある日が1週間で2回、日曜日は休演)、日本は9~10公演(マチソワが週3回、休演日は週1)。
俳優さんも疲弊するが、俳優さんが出勤する前後も劇場や舞台を整えるスタッフさんはもっと疲弊する。寝不足していれば手元が狂ったり足を滑らせたりして命にかかわる事故を起こす危険だってある。
変化すべき日本ミュージカル界
このように、日本のミュージカル界には技術・音楽・演者それぞれ世界に誇るべき人材がありながら、労働形態と経営に様々な問題を抱えている。
それは長年の悪習だったはずだが、今まさに表面化してきている。
コロナによる海外交流の断絶や戦争による経済のひっ迫から翻訳ミュージカルに頼ることができず、日本は昨今で国産ミュージカルを量産するようになった。それを受けて、これまで押し通してきた古いやり方や考え方が通じなくなっている。
国産ミュージカルをゼロから作るということは、海外で既に上演されている作品の資料映像も既成の台本もないということ。答えが分からないから、すべてが手探り。したがって翻訳ミュージカルよりも稽古場でやることが多いのは当然。
だとしたら、どのくらい多くの時間が必要になりそうか、新たに見積もりを出すところから始めなければいけない。
変化すべき時が来ているのだ。労働者の給料の払い方から稽古期間、上演回数に至るまですべての問題を洗い出し、その根本原因を探り当てる。時間が多少かかってもコツコツと解決していく勇気が、日本ミュージカル界を引っ張るリーダーたちに必要とされている。
新しい一歩を踏み出すことは恐ろしい。しかし、変われないことはもっと恐ろしい。

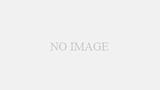
コメント